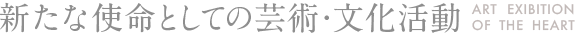『曙光』
鈴木さんは丘の上病院に入院して6ヶ月後の1987年4月、退院することになった。しかし、また入院前と同じことを繰り返すのではないか、という不安があった。そのため、週2回の「造形教室」に通い、継続的に制作に取り組むことで、アルコールへの依存、肝障害などからの脱却を図ろうとしていた。しかし、夫は「退院したのだから、精神科に通う必要はない」、そして「絵なんて無意味、無駄だ」とも言い続けていた。難色をしめす夫とのあつれきはあっても、自由に描け、また彼女自身が一番なじめる「場」を求め、彼女は「造形教室」に通い続け、初めての油絵を完成させた時、『曙光』と題した。苦境の中から再生を懸けた最初の作品への思い入れの深さがうかがえる。作品はその後、都民展に出品し、入選。これまで繰り返してきた生活からの脱却を図ろうと期し、その感触をもつことができた。以後毎年、都民展に出品。それまでは、家に込もって寝床に伏しがちで、小・中学生の息子たちに家事をやってもらわなければならないほどだった。その彼女の、子供や夫に対する態度が変わってきた。夫はその変化、効果は認めるようになっていった。
『車窓』
ある時、彼女は唐突に夫の写真をもとに油絵を制作し始めた。夫への絵を介したメッセージ。「夫には内緒です。出来上がったら都美術展で観てもらうつもり」と話していた。出品を前に画材店から届けられた額縁は真っ黒い額縁だった。「なんだか喪中の額みたい」と気にかけ、別の額に入れ換えて出品した。美術館でこの絵を観た夫は「自分がこうであったらいい、と思っていたような姿に僕を描いてくれた」と言って喜んでくれた。結婚以来、夫との間にあった疎隔感はこの絵の制作が機となり「和解」へ。しかしその数日後、夫は会社の忘年会の帰り、自宅前で転倒、脳挫傷で意識不明のまま医療センターで亡くなる。これまでの一連の出来事が夫の重大事にことごとく符合していたことに、私たちは愕然とさせられた。彼女が突然(急いで)夫の肖像を描いたこと。届けられたのが真っ黒い額縁だったこと。そして、夫が思いのほか喜んでくれたことなど。まったく予想もしなかった突然の重大事が起こる前、何かの前触れのことを、「虫の知らせ」という。客観的な原因や因果関係では解くことのできない超常的現象について、C.G.ユングは「共時性(シンクロニシティ=意味ある偶然)」と述べている。
『グリーフ・ワーク連作』
夫との死別後、彼女は急性悲嘆の状態で自宅にこもる毎日だったが、一緒に絵を描いている仲間達の励ましもあり、「たとえ描けなくても」と「造形教室」に復帰。体調の許すかぎり通い続けた。「とても絵にはならないが」と言いつつも、その時その時の心のうつろい、内に潜む感情をパステルで素描し続ける。この時期のスケッチブックに描き続けられた一連の作品は、彼女にとって絶望、抑うつ、不安、孤独感などを絵に表わし、再出発への心の準備をなす「グリーフ・ワーク(悲嘆の仕事)」としての作品に他ならない。
『暮明のなかの回廊』
「なんとか現在の私の心境を表わし、これからの出口を模索する作業として油絵を再開したい」と2年ぶりに大きなキャンバスに取りかかる。この途中も浮き沈みの繰り返し、油絵の途中でパステルの素描画を描くだけの時期もあった。しかし、99年末、入院先の医療センターで他界。夫の死から3年後のことだった。
(エイブル・アート・ジャパン編『“癒し”としての自己表現』より抜粋)