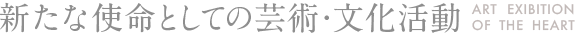『“風景画”としての自画像』
絵は、枠に囲まれた平面の静止画像なのだが、回を追って一枚一枚徐々に推移、変化、深化していく様子が、まるで動画のように、そのときそのときの内面の動きが活写されている様子が見てとれることがある。一枚ずつを見る限りでは、同じ繰り返しのようにしか見えていなかったものが、その変化のプロセスがはっきりと刻印されていることを発見、あらためて驚かされることがある。絵画は立体的、時間的な表現の世界なのである。
「造形教室」に通う30代前半の男性患者が毎週一枚ずつ、1年2ヶ月にわたって50数枚の自画像を描き続けた。
当時2年間部屋に閉じ篭りの生活、家族とは一言も話さず緘黙(かんもく)し続けていた。後藤さんも多くの患者と同様に、“不器用、絵は苦手”と言っていた。自画像を描くようになる前、木彫や幾何学模様の彩色画、自動表記法=スクリブルといわれる即興画などを手がけた。そのことが彼自身の足場をつくるための入門の儀式、助走の段階にもなっていたのだろう。
その後、正面向きで上半身の自分の姿を毎回描いていった。硬い輪郭線でなぞられた人物はいつも困惑したような表情で直立していた。自分をとりまく圧迫感のなかで身動きがとれないでいる様子がひしひしと伝わってくるようであった。
くる日もくる日もまったく同じパターンの繰り返しに見えていたものが、実は静かながらも着実に変容していた。硬い表情は徐々に和らぎ、くすんでかさかさしたような皮膚に潤いがさし、生気がよみがえった。そして、正面を茫然と見ていた顔はゆっくりと向きを変え、斜め前方に柔らかい視線を向けていった。
べた一面に塗り込められていた平板なバックに雲が描かれたり、木々や街の情景も描かれていった。硬く固定されていた彼の目が自然にうつろいゆくままに窓からの眺め、目の前の事物など自在に描き込まれ、点景、配置されていった。絵の描き方が上手くなった、明るくなったというようなことは表面的な現象に過ぎない。何よりもまず強く印象付けられることは彼の閉ざされていた心が内側から開かれてゆき、それと同時に彼のいる外界が奥行き(パースペクティブ)を深めていったことだった。内面の変化とともに外部の情景が広がりをもって現れはじめた。平面の静止した絵が自由に活動し、立体的な空間を拡げていった。彼のゆるやかなそしてダイナミックな絵の変遷はこのことを象徴的に表しているように思う。
(安彦講平)
(『心の杖として鏡として-“癒し”としての自己表現』より)