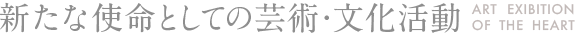今回、展覧会のテーマを「臨“生”芸術宣言! ~生に向き合うことから〜」としましたが、“生”に臨むということは、それは裏を返せば“死”に臨む、あるいは臨まされている、という状況でもあるんです。死が遠いことであったり、他人事なんかではなく、まさに今、私自身のこと、私の日常において死がとてつもなく身近に感じられるからこそ、“生”に臨むのです。臨まない訳には、いかないのです。どうして、こんなことになっちゃったんでしょう。何故、こんなにも生きにくい“生”を引き受けなくてはならないのでしょうか。これは何か人智を越えた、深淵な意味があってのことなのでしょうか。ともかく、この道を歩むしかないのです。
2009年以来、継続してきた「心のアート展」に集まる作品群。苦難・苦境の中から、切実さを持って生み出され、表現された作品の数々に、「既存のアートにはない感動がある」、「日常の中で失われていたかのように思っていた“生”の感覚、リアリティーが呼び戻された」など、毎回、多くの共感・共鳴の声が寄せられています。おそらく、観に来て下さる方々もまた、それぞれに「生きにくさ」を抱えながら、日々を過ごしているのでしょう。だからこそ、苦難・苦境の中から生み出されたこれらの作品群に、人々は自からの身を重ね合わせ、生きにくい“私”の存在を、それらの作品によって受けとめられ、受け入れられ、感動と共に勇気や希望を見出していくのではないか、と思うのです。
“生命”というのは、なんとも矛盾した存在です。生まれたその瞬間に、死へと向かう運命を歩み始めるのです。生きるということは、死という全く正反対のベクトルを抱え、抗(あらが)いながら、その命が尽きる最後の瞬間まで生き抜こうとする営みなのです。もしかすると「生きにくさ」の根幹には、こういうことがあるからかしら、とも思います。そして、生きようとするエネルギーと、死へと向かうエネルギー、その相反するエネルギーの激しい拮抗、引き裂かれる軋(きし)みが、この展覧会では表現というエネルギーとなって噴き出しているかのように思えるのです。
本展のメインとなる〈公募作品展示〉は、回を重ねるごとに応募作品数、応募者数が増え続け、今回も質実多様な「臨“生”」の表現たちが数多く集まりました。展示会場の壁面に限りがあるので、すべての応募作品を展示することは叶わず、悩ましい審査をする訳なのですが、一次審査、エ次審査とも、審査員の先生方は、一点一点の作品と出逢い、心を揺さぶられながら、本展の趣旨に沿って、真摯に審査をなさっていました。そして多様で豊かな“生”の在りように、驚くともに安堵し、「今回もいい展覧会になる」と確信されていました。
ところで今回、〈特集展示〉として近代日本洋画史で異才を放つ夭逝の画家・関根正二を紹介します。詳しいことは会場での展示を観ていただくこととして、彼もまた「生きにくさ」を抱え、「絶望」の淵にありながら、むしろそれを表現の源泉・バトスとして、自らの“生”に真っ正面から向き合い、表現を通して強烈な光を放った“生命”でした。彼のような存在は、わたしたちのような「臨“生”」の芸術を志向している者にとっては、非常に勇気を与えてくれる光のように思います。
また、今回はこの〈特集展示〉の他に、〈特別上映〉とし2015年にブラジルで製作された映画『ニーゼと光のアトリエ』を会期中に3回、展示会場と同じフロアにある別会場にて上映をおこないます。ロボトミーや電気ショックといった治療法しかなかったような時代、しかも第二次世界大戦中の1944年に、病院内に自由な表現の場を作り、アートを通した癒しの実践があったというこの事実には本当に驚かされます。人間が人間らしく、その人がその人らしく生きる(活きる)ために、何が必要か、どういう関わりや関係性が必要なのか、この映画は医療の領域だけにとどまらず、すべての人にとって示唆的な内容が、あちこちにちりばめられているように思うのです。
こうして編集後記を書いていると、いよいよ展覧会が始まるのだな、と身が引き締まる思いです。これを書いている今、まだ展示の準備は全然出来ていませんが、今回もきっと充実した、他にはない素晴らしい展覧会になると思います。もし展覧会場に、映画の主人公である、実在した女医・ニーゼが足を運んでくれたならば、大いに喜ぶであろうと思います。また関根正二が会場を訪れたならば、それぞれの作品を嬉しそうに、そして興味深く熱心に観入ることだろうと思います。
人間は、苦難・苦境の中にあっても、命ある限り精一杯その与えられた“生”に臨み、表現する存在なのであり、しかもそのパトスからの深淵な表現は、強烈な光を放ち、観る者に迫まり、問いかけてきます。そしてこの光こそは、人類がその生命活動を子々孫々、繋いでいく中で、その道を照らす欠くことのできない大切な光であるように思うのです。わたしたちはここに「臨“生”芸術宣言!」をします。