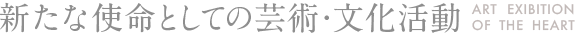かつて厳格に隔離されていたハンセン病療養所の中で、自らの死期を察して、すべての原稿を焼き捨てた詩人がいた。この病気は、古くは「癩病(らいびょう)」と呼ばれ、現在からは想像もできないほど、謂れなき苛酷な差別を被ってきた。そのため療養所に入所した患者の多くは偽名を用いて身元を隠し、死後に親族へと累が及ばぬよう、ひっそりと持ち物を処分する人々の姿がしばしば見られたという。おそらく、この詩人も同じような境遇にあったのだろう。
しかしながらまた一方で、ハンセン病療養所は、患者たちの手によって豊穣な文学作品が生みだされた場所でもあった。この詩人も、死に際して原稿を焼き捨てねばならないような境遇にありながら、生前はむしろ表現することを決してやめなかったのである。社会から完全に隔離された患者たちにとって、自分の苦しい胸の内を原稿用紙に書き綴ることは、自分がこの世に生きている意味と証を必死に模索する営みでもあったのだろう。患者たちの文学は、時に宛先もないまま綴られる孤独な営みではあったけれど、しかしその根底には「自分が生きている痕跡をこの世界に刻み込むこと」への情熱が確かに脈打っていたのである。
ハンセン病患者たちの文学に対する情熱に想いを致す時、ある精神科病院の造形教室で出会った一人の男性のことを思い出す。かつてのハンセン病療養所と現在の精神科病院と、医療施設として同列に比較できるはずもないが、しかしこれらの表現者たちは、共に「人間にとって表現とは何か?」という問題を考える上で非常に重要な問題を投げかけてくるのである。
この男性が描いた多くの絵の中に、特に記憶に残る2枚がある。1枚は怒りの感情を露わに仁王立ちする怪物(モンスター)の絵。もう1枚はカジュアルな服装で優しく微笑む女の子の絵。どちらもA4のコピー用紙にシャープペンシルで描かれているが、前者は紙に穴が開きそうなほど濃密に筆が重ねられ、観る者の網膜を切り裂かんとするかのような迫力がある一方、後者は割りと軽いタッチで奔放に描かれている。作者は「僕は心のバランスをとるために絵を描きます」と言い、ほぼ毎日このような絵を描いているという。そんな作者と約1年間ほど話を重ねた頃、彼にとって、どうやら前者のような絵を描く時の方が心の調子が良く、むしろ後者のような絵を描く時の方が不調であるらしいことに気付いた。私は漠然と、調子の悪い時は怪物を描き、良い時はカジュアルな絵を描くのだろうとばかり考えていたのだが、どうやら事態はそれほど単純ではなかった。それまで私は、何とか彼の絵にこめられた意味を「解釈」しようと躍起になっていた。しかし彼と話を重ね、彼の人生や絵に対する思い入れに「共感」する気持ちが芽生え出した頃、劇的に絵の観え方が変わってきたのである。
普段、私たちは「心の調子が良いこと」、つまり「心が〈健全〉〈健康〉であること」とは、すなわち「心に〈闇〉がないこと」と考えてしまいがちである。しかし考えてみれば、心に一片の〈闇〉も持たない人間などまずいない。誰もが悲しみ、落ち込み、怒ったりするように、人の心には程度の差こそあれ陰鬱な思念や暴力的な発想は存在するし、直面する状況次第で誰の心にも必ず芽生える。それは喜びや楽しみの反面として必然的に存在するのであって、〈闇〉それ自体が悪なのではない。むしろ優れた芸術が悲嘆や苦悩から生れるように、心の〈闇〉は時として創造力や行動力の源泉とさえなる。重要なのは、抱え込んだ心の〈闇〉といかに向き合い、いかに対処するかなのだろう。
彼にとって絵を描くことは、喩えるなら心の〈浸透圧〉を調整するようなもので、高まり過ぎた感情を怪物に託して吐き出すことができる時は調子が良く、そのような絵が描けない不調の時は和やかな絵を描いて飲み込むことで、煮詰まり過ぎた心の濃度を下げているのではないだろうか。そして本当に調子が悪い時は、絵を描くことさえできない時である。彼(の絵)との出会いは、私に「人間は心の〈闇〉を呼吸しながら生きる存在である」という事実を教えてくれたのである。
殊更に絵画や芸術に限らずとも、人間が生きること自体、ある意味では表現の連続である。身近な人に自分の思いを伝えることも、微笑むことも泣くことも、あるいは絶叫することも沈黙することも、広い意味では表現である。他者の表現を受けとめることは、肯定的に捉えるにせよ否定的に捉えるにせよ、少なくともその人の存在を受けとめることであり、また逆に、自分の存在が誰かに受けとめられていると素朴に信じられるからこそ、人は普段さして意識することもなく自分を表現しながら生きていけるのだろう。表現とは受け手が存在して初めて成り立つ営みであり、人がある程度の苦しみや悲しみに耐えられるのは、その表現を受けとめ、心の重荷を分かち合ってくれる人との関係性があるからだろう。
もしかしたら〈心を病む〉ということは、このような関係性自体が病むことを意味しているのかもしれない。〈心を病む人〉とは、喩えるなら、苦境に曝され悲しみや憎しみで心がパンクしそうな時にも、その感情を吐き出すことができず、自らの心身を責め苛むという形でしか表現できない人のことなのだろう。あるいは苦しみを表現しても誰にも受けとめてもらえず、自分という存在がまるで虚空へと投げ出されてしまった人のことなのだろう。またあるいは、私たちは普段〈常識〉や〈社会通念〉といったものを身につけていると信じて疑わないが、そのような価値観では受けとめきれない表現をする人のことを指して〈精神病者〉や〈精神障害者〉と呼んでいるのかもしれない。
先の絵の作者は、病むことを経験して、絵を描くことへの執着心が増してきたという。「何億回、不安発作と自殺未遂をしたか分りません」という彼は、どんな時も絵を描くことをやめなかった。入院した急性期病棟の中で、強い薬で朦朧となり点滴と尿道カテーテルを着けられていたような時も、また不安発作が治まらず身体拘束を受けていた時も、食事などで拘束が解かれる瞬間を見計らって絵を描き続けてきた。彼の絵に対する執着は生きることへの執着であり、今回の展示会の副題を借りれば、描くことはまさに「生命の証」であったのである。生きるための表現を続けてきた彼が心を病んでいるということ(あるいは病んできたということ)は、むしろ彼の表現と向き合う私たち一人ひとりが受けとめ、考えなければならない問題なのかもしれない。
事態はここまで深刻ではなくとも(あるいはもっと深刻な人もいるかもしれないが)、今回展示された作品の多くも、自らの存在の意味と証を模索するかのような、切実で真剣な表現ばかりであるように思われる。第一回展に引続き、今回も公募作品の審査会や諸々の準備を(少しばかり)手伝わせて頂く好機を得たが、これらの絵に触れる時は緊張に心が張り詰め、濃密な時間が流れていたように思われる。
優れた芸術表現は、人々の安易な想像力やお節介な意味付けを超えてみせるところにその魅力があるだろう。例えば、一見陰鬱で暴力的な絵が、自らの心の〈闇〉を吐き出せるエネルギーと、それを受けとめてくれる仲間たちへの信頼に支えられた崇高な人間讃歌である場合も、また逆に一見明るく朗らかな絵が、孤独の内に抱えた〈闇〉を紛らわすための苦悶の絶叫である場合もある。絵は平面に描かれた二次元的な芸術ではあるけれども、その表現は極めて複雑で多元的な場を土壌として初めて生れてくるものである。今回の出展作品が生み出された背景にも、個々の作者の語り尽くせぬ思い入れや、各病院が工夫を凝らした造形教室の努力など、まさに「無形の営み」の蓄積が存在するのであって、それは簡単に「解釈」できるほど単純なものではない。
ご来場頂いた方々には、是非とも、表現の意味や意図を一方的に「解釈」するのではなく、その表現が醸し出す存在感や雰囲気に「共感」することから始めて頂きたい。キャンバスの背後に沈潜する「無形の営み」にも想いを致すべく心を開いた時、絵は、その複雑な表現の綾から滲み出る「声なき声」を伝えてくれるだろう。