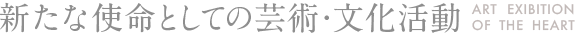『初めに〈絵〉ありき』 −つぎつぎに運びこまれ、画架に掲げられた作品を目の前にし、まず、じーっと凝視する。かっと目を見開き全体を眺め入る。視野焦点を移して色・形・動きを辿り、ディティールに分け入る。胸の内にとよめくものをじかに聴き入るように腕組みし、内なる観想をめぐらせているかのような……あの時、その現場に居並ぶ審査員。五者五様のただならぬ立ち居振る舞いは、まるで絵画作品という舞台背景に立会い、言葉にならない感興を全身で確かめ、独演・共演のオムニバスドラマがかもし出されて行ったかのようなひとときだった。
これは、2009年12月18日に行われた第2回「心のアート展・生命の証~芸術の力、新しい使命」の審査会の光景だ。作家、精神科医、医療文化・人間学、臨床医などなど、未だ途上にある私を除けば、それぞれの専門領域で大きな仕事を果たしてきた方たちだ。だからこそ、これらの作品と出遭ったその瞬間から、審査員席という定位置から降りて、それぞれ思い思いの視線、観点、姿勢で絵に向き合っていた。無心・無垢な状態に往還できたのだと思う。そして、この作品と作者たちは、このような出遭いをこそ希求していたのだと思う。
一作一品の内に刻みこまれているもの、つきつけてくるものによって触発・喚起され、まさに“無形の営み・有形の結実”というもうひとつの“作品”が創出されていったごとくに。優劣、順位、合格不合格を一斉採択する「審査会」なるものとはおよそほど遠い、双方向からの共振共鳴の場・プロセスとしての時・空間。「心のアート・生命の証」展の助走は始まった。
通常、絵は枠で仕切られた固定、静止した画面と見なされているが、それぞれの見方、観点、拠って立つ位置によって絵は入り口、間口、奥行きを自在に開き、閉じ、深く、浅くへ、と変容していく。絵は観る者の姿、内面を写す〈鏡〉といえよう。
第1回「心のアート展」は昨年2月24日~26日、土日の休日をはずれた平日の3日間だけの短期間の開催だったが、予想を超えて多くの人が来観。何よりもアンケートに書きこまれた文、ギャラリー・トークで語り、交わされた言葉は、賞賛や共感を超えて、それぞれの内面、切実な意思表示がこめられていた。「すぐれた感性とひらめきを放つ作品が多いのに驚きました」、「心に病いを持つ方の絵?でも会場に入るなり、そのバイアス、思いこみがぶっ飛び、あらためて“生きるとは?”と自分に問いかけています」。
そして、このような提案も。「“心を病んでいるか否か”を意識せずに観ている。なので今回、特に“心の病い”を頭において作品を観ることには違和感を覚えてしまうのです」、「第2回展の審査員には、画家を加えるべき。それにより、優れた作品が広く世間に知られていく筈だから」。私自身、共感・納得しながらもしかし、生きる杖としての、他にかけがえのない表現が〈障害者アート〉〈美術専門〉などなど、仮設の境界、段差を超えて、生命の深淵、無限の可能性を索め、表現の原点に根ざし、試行する営為ではないか。
第2回「心のアート展・生命の証~芸術の力、新しい使命」も多くの人に来観していただき、参画し、語り合って行きたいと願っている。