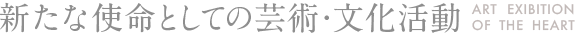僕は、平川病院〈造形教室〉のスタッフで、「心のアート展」の実行委員をしているが、休みの日はもっぱら自然栽培で野菜を育てている。自然栽培とは、簡単に言うと農薬も肥料も使わない自然の法則に従った栽培方法なのだけど、一般的には無施肥・無農薬では、まともな野菜は育たないと信じられているし、時には何かの宗教じゃないかと受け取られたりもする。ところが、そんなことはない。畑の環境を整えるのに時間はかかるが、自然の摂理にのっとったバランスのとれた土壌が出来てくれば、野菜は本来の生命力を発揮し十分に育つし、僕は何かの宗教をやっているわけではない。
「雑草も野菜も、みんながそれぞれ活き活きと共生しているような風景」を夢見て始めた畑仕事。15年くらいの経験しかなく、まだまだ勉強中の身ではあるが、土をいじり、つぶさに自然を観察しながら試行錯誤を繰り返していると、色々な気づきがある。「自」ら「然(しか)」るべき自然の在りようという神秘に触れることで、道理というものが分かってくるような、身に付いてくるような、そんな気がしてくる。そして、これまで常識だと思っていたことが覆され、思考が拓かれていくように感じる。
畑において雑草は、野菜の栄養を奪ってしまうので根こそぎ取り除くものだと思われているが、実は雑草はとてもありがたい存在で、長い目で見れば養分を奪うどころか、むしろ畑の土壌を豊かにしてくれることが分かってくる。雑草がそこに生えているのは、今その土壌にとって必要だから生えているのであって、やみくもに生えている訳ではない。だから畑の土を豊かにするために、その雑草の地表部分だけを刈り取りその場において置く。すると、刈られた草が土に還り、その土壌に不足していた養分が補われたり、崩れていたバランスが整っていったりする。
土が痩せているからといって、その土地にはない肥料を、他所から持ってきて補ってしまうと、その環境で循環するはずの自然のサイクルが出来てこない。そこから生まれて来たものを、ただただその場に還すということを繰り返すことによって自然のサイクルは回りだし、土は豊かになっていく。すると、生えてくる雑草の種類が自然と変わってくる。土壌が必要としているものが変わり、そこに生えることの出来る雑草の種類も変わるからだ。
野菜を育てていると、虫がついたり病気になったりして、上手く育たないことがある。これもよくよく観察していると、自然の摂理にのっとった必要不可欠なことのようだ。虫がついたり病気になるのは、その土壌にある不必要な養分を取り除いたり中和するためのようなのだ。だからそのままにしておいて、やり過ごすより仕方がない。防虫剤や農薬を使うと、自然の浄化作用が働かなくなってしまう。野菜が育たなくなるのは、その時は困ったことではあるが、長い目で考えると必要なことであり、むしろありがたいことなのだ。
こうして自然の摂理を大切にし、抗わないように育てた野菜は、信じられないかも知れないが腐らなくなっていく。おそらくスーパーなどに置いてある大抵の野菜は、放置しておくとやがて腐る。一方、自然栽培の野菜は腐らずに、ただただ枯れる。野山に自生している木の実などは、やはり腐らずに枯れる。たぶん、枯れるのが本来の姿なのだと思う。でもスーパーに置いてある野菜や果物は腐る。腐るのには、きっと色々な理由があると思うが、その一つとして栄養が豊富だということがあるのだろう。過剰な養分をバランスのとれた状態に戻すための自然の浄化作用として腐るのだと思う。
スーパーに置いてある野菜は栄養があり、それはそれで結構なことだと思う。それらの野菜は色ツヤ、形も良く、大きさも圴一になっていて見た目もいいので美味しそうだ。美味しそうに見えることは、農業で生計を立てるためには、とても重要なことだ。大きさや形は物流の面で、とても大事な要素だ。それはわかる。でも、野菜を趣味で育てている僕は、のんきにもそこに不自然さを感じてしまう。スーパーの野菜に比べ、色ツヤもそこまで良くはなく、時に曲がりくねり、大きさもまちまちの不揃いな野菜たち。でも雑草と共に育ち、野性味溢れる個性的なその姿を、愛おしく感じてしまうのだ。
そんな自然栽培を通して自然との共生、バランスを大事にすることを心がけていると、不思議と〈造形教室〉の日々の活動が重なって見えてくる。〈造形教室〉を主宰する安彦講平先生は、自身の活動の一側面を「開拓開墾=cultivate=耕作=culture=文化」に例えて話しをすることがあるが、畑をやっていると、つくづく真にそうだなと深く納得する。病院内で自由な表現の「場」を営んでいくには、土作りという目には見えない水面下での営みを抜きには考えられない。豊かな土壌が在ってこそ、そこで野菜は自らの持っている生命力を存分に発揮することができる。それぞれが表現する主体となり、豊かに文化を育んでいけるのだ。
これはある意味とても簡単で、あたり前のことではあるのだけれど、実践するのはそれほど容易ではない。なにしろ、人間が作りだした不自然な「常識」に知らず知らずのうちに囚われていて、ついつい善かれと思って雑草を抜くようなことをしてしまったり、肥料や農薬に頼ったりということをしてしまう。自然の摂理に沿うよりも、人間の都合や理屈を自然の側に押し付けてしまいがちなのだ。だから、自然の力を信じて余計なことをしない、そして自然に必要とされていることを見極め行動する、というのは案外に難しい。ましてや今の時代、ますます効率や生産性、スピードなどが求められ、自然体でいるよりも、より人間的に意図的に行動することが求められるので、自然の声に素直に耳を傾けるというのは簡単ではない。
本来、人間は自然の前ではちっぽけな存在でしかないのだ。「自然」というと、豊かで、やさしく、心地の良い側面が思い浮かぶかも知れないが、むしろドロドロとしていて、人智を遥かに超えた恐ろしいほど剥き出しのエネルギーの蠢(うごめ)きでもあるのだ。例えば、福島第一原発による放射能汚染によって帰還困難区域となっているあの光景。汚染された苛酷な環境の中で、家畜だった牛や豚、飼われていた犬や猫、イノシシなどの野生動物、大地の草花や森の樹々が、人間の手による管理や制約がなくなったことで自然のエネルギーを剥き出しに、人知れず蠢いている。大気汚染も土壌汚染も海洋汚染も、そしてその土地にあったあらゆる人間らしい営みを侵蝕し呑み込みながら、狂おしいまでの光景に変貌している。自然とは、人間を遥かに超えたものなのだ。
ところで、日本を代表する思想家の一人であり「民藝」という言葉を作った柳宗悦は、それまで美の対象として顧みられることのなかった工芸品や雑器、下手物(げてもの)と呼ばれる不断遣(ふだんづか)いの安価な雑器の中に、「健康な美」や「平常の美」、「用の美」といった「美」の相が豊かに宿ることを発見した。それらは自然の原料、その土地の恵みを用いて作られる。だから地域によって生み出される工芸品は、当然のことながら異なってくる。工芸は、その土地の自然に深く根ざしているものなのだ。
また、工芸は代々受け継がれてきた伝統にのっとって作られる。長い年月をかけ、地域の気候風土と折り合いを付けながら、自然の摂理、自然の意志に沿い、その環境を生きることによって伝統は育まれていく。人間を超えた大いなる存在の中で、もはや自然の一部と化した職人の手仕事によって、「美」はその土地のものとして結実する。民藝における「美」とは、作り手の自我によって生み出された装飾的で美術化された自然からも実用からも離れた工芸品にではなく、地域の自然に深く根ざし、その土地の気候風土を生きることによって育まれた実用のための身近な工芸品にこそ宿るのだ。
そしてその「美」は、美醜を越えた「美」であると柳宗悦は言う。醜の対義語としての美ではないのだ。人間は様々な「二元」に引き裂かれている存在で、どこかに拠り所を求めても永遠や絶対というものはなく、全ての物事は移り変わる「無常の世界」を生きている。生死、自他、善悪、上下など、世の中にはありとあらゆる二元があり、それがあるからこそ人間は世界を認知、知覚できるが、一方で二つの相のただ中にあるからこそ、人間は実相、あるいは本性という本来的な在り方から引き裂かれ苦しみを背負って生きる。
そこで彼は「二にあって一に達する道」として「自然」ということを考えた。僕の解釈がどれほど言い得ているかはわからないが、人間はそもそも自然の一部であり、自らの身体を通して自然に繋がっている。自然を通して実相、あるいは本性に還ることも出来るし、自らを自然から切り離された存在と捉え、二つの間の絶えざる矛盾の中に彷徨うことも出来る。工芸は土地の自然と深く交わった生活から生み出される。工芸品を作る中で自我を離れ自然に帰依する時、そこに「美」が宿る。民藝における「美」とは二元を越えた、あるいは美と醜の二つが未だ分かれぬ已前(いぜん)の「美」なのだ。
柳宗悦の「民藝」から見えてくる風景は、僕の中では自然栽培とも、〈造形教室〉の活動とも、そして「心のアート展」の活動とも実によく重なっている。前回の第6回「心のアート展」では「臨“生”芸術(りんしょうげいじゅつ)」を勝手に「宣言」した訳だけれども、今回も、展覧会準備をしながらつくづく感じたのは、この展覧会活動の根幹には、まさに「臨“生”」があるということだった。
表現をすることで自らの生(せい)に臨(のぞ)む。生に臨むことによってそこに表現が生まれる。「生きる」という太古から変わらぬ人間の、いや生命にとってあまりにも自明で本質的なことが、この時代、この社会の中においては、どうにもやさしいことではない。人間的な都合、理屈が優先し、自然から離れた生活の中で、それぞれの身体に潜む自然が疼(うず)き、本来的な“生”へと臨む表現が噴出する。「心のアート」が表現を通して臨んでいる“生”とは、生死の二元を越えた“生”なのだ。だから差し出された表現を前に、人は自然に、自らを観るのだろう。
これが「心のアート展」に集まる作品群の魅力ではないかと思う。自らの本性へと向かう、あるいは向き合うその表現が、同時代を生きる人たちにとって切実な表現として共感を持って受けとめられ、心を拓いていく。苦難・苦境からの表現が、この時代、社会において、より深淵な意味を孕(はら)んで立ち現れてくるのはそのためなのだ。今回、展覧会のテーマを『境界を越えて —生の原点に還る—』とした。二元を越え、“生”に臨み、本性へ還る。アートのためのアートではなく、商業的なアートでもなく、障害者アートでもなく、全ての人に通底する本質的なアート、「心のアート」に特有の“美”を宿した風景がここにはあるように思う。