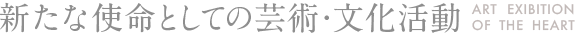2009年2月に第1回「心のアート展」を開催して、7回展10年目。これまでの歩みを振り返ると、この活動は、まさに文化(culture)の語源であるラテン語「コレレ=colere」――開拓開墾、未知未開の地に分け入り地ならしして、播種施肥し開花結実を目ざす、その繰り返しと言えよう。
ほぼ隔年で、池袋の東京芸術劇場で開催してきた本展は、困難な時代のなかに生きる人々の、ここにいる現存在を広く社会に発信し、問いかけるためのささやかな一つの土壌を作ってきた。第7回の今年もまた、作者が苦難苦境を拓きながら、自らの「生」に向き合ってきた証しを提示し、さまざまな人と交流する、そんな場を創ってきた。「心のアート展」の審査は一般の審査――優劣、順位を決めるコトとは異なっている。審査員は作品を通して作者それぞれの「生」に真摯に向き合い、作者が感知した、時代・社会に底在する「無形の形、無声の声」の一片を掬い上げてきた。
「心のアート展」は各回ごとに独自の多様な道程があり、それぞれ異なる深みと広がりを孕んでいる。ピラミッド式に積み重ね、物量的、数値的な進歩成果を目指してきたのではない。アートという営為は、一回が終わればまた原点に還り、次の新たな航行に向けて出航する。順風満帆ではない荒海の中での航法であり、海図のない中での一回性の出会いであるように思われる。一回性だからこそ、原初のアートにも新鮮な驚きがある。
「あっ、牛だ。牛が走ってくる」――と、子どもたちが出逢い「発見」した、旧石器時代の人類初の芸術、ラスコーの洞窟壁画。現代人の描くいわゆる前衛的な絵画。それぞれをその時代の状況や、作者が置かれた環境の中で生まれた一回性の営為として観るとき、その表現の質と実は同根ではないだろうか。「心のアート展」は一回性の営為のなかに表出した、新鮮な驚きのある「生」の表現を、回ごとに掬い取ろうと試み向き合ってきた。
「生」に向き合う――それは「臨“生”」ということだと思う。一般に言う「臨床」とは、治療や援助を求める人々に寄り添い、援助・看護・治療を施してあげる“コト”。しかしこの語は、「床」に伏している病者・障がい者・弱者を、上から見下ろすという意味が含まれるように思われる。そこに内在する助けて「あげる」という空気は、支配・被支配、能動・受動の、上下関係を作り出している。だが、こうは言えないだろうか。人間は誰もが生老病死という多事多難に満ちた生命の自然な営みの中で生きている。思いがけない病気、災難に遭遇し、痛みや苦しみに身をもって向き合うことではじめて、生命の営みの深層を身をもって知り、学ぶことができる。当事者を見下ろすのではなく、災厄を知る人=当事者として真摯に向き合ってこそ、私たちは知らなかったこと――人智、技法では量り知れないすべての生命体、天然自然の未知未開の深淵の一端を学び、気づいていく。
さて、私自身の活動の原点に立ち還る。私が東京足立病院の精神科病棟で、入院患者さんたちと共に〈造形教室〉を始めたのは1968年。東欧では「プラハの春」が自由を求めて萌え出で、西欧ではパリの「五月革命」で学生や市民が一斉に蜂起した。日本では安田講堂占拠などの学生運動が盛んになり、また永山則夫による連続射殺事件が社会を戦慄させたのもこの年だった。そしてWHO(世界保健機関)から派遣されたD・H・クラークが当時の先進国のなかでも圧倒的に多い我が国の病床数・長期在院日数を憂慮して、社会の中での精神衛生の推進こそ急務とすべきとの「クラーク勧告」を日本政府に提出したのも、同じ年になる。このような激動の年に<造形教室>を創始することになったのはC・G・ユングの言うシンクロニシティ(共時性)、「意味ある偶然」だったと思われる。
翌々年、鍵も格子もない完全開放制の精神科病院として知られる、八王子市の丘の上病院の要請に応じ、同院でも〈造形教室〉を開いた。当院は多様活発なアート活動、患者さんのアートを実践する熱気あふれる空気があった。丘の上病院は1995年に閉院したため、平川病院に活動の場を移して今日まで継続している。また茨城県の地域社会に根ざした精神医療を目指す袋田病院でも教室を開いている。過去には武蔵野中央病院、那覇のかいクリニックでも、同様の教室を開催していた。
〈造形教室〉は、「治療」や「教育」といった、上から与えられ、課せられ、外から評価、解釈されるものではなく、それぞれが表現活動の主体となって自由に描き、身をもった自己表現の体験を通して、その人その人に内在する個性、可能性を引き出し、自らを“癒し”支えていく「営みの場」、といえるのではないだろうか。それぞれが、さまざまな画材を使ってその時、その場で、思い思いに表現し、語り合っている。自作の詩・小文などの朗読やギター演奏もある。〈造形教室〉のアトリエは有形のモノを創りだす場で、同時に人と人との関係性という無形のコトを創り出す場、営為である。しかし決して平和な、和気あいあいとした場だけではなく、今までの人生で出せなかった内面、人との関係が表れる場でもあるように思う。
そんな環境のなかから生み出された作品を市民に観てもらおうと、街の中の公共施設で「“癒し”としての自己表現展―心の杖として鏡として」を始めたのは、1992年。病院内での活動、地域社会との連携を越えて、受難受苦=パトスから生み出されたアートと、さまざまな境遇の人との出逢いの場を創出することを目指し続けてきた。 “癒し”としての自己表現を血肉化してきたのは、ここを他に代えられないかけがえのない場として通い続け、表現し、語り合ってきた沢山の患者さんではないだろうか。その患者さんとの出逢いにこそ、学び、教えられ、鍛えられることがあり、今の自分がある。
〈造形教室〉の創始から50年以上。そんなに長い年月に相応するだけの成果や先の見通しを開拓し得たという実感はない。むしろ今まで気づかなかったこと、見えていなかったことなど、毎回毎場、ありありと身体全体で感じられる。一刻一瞬が時計や暦で計る時間とは違う、長い永続的な時間としてあるように感じられる。〈造形教室〉に通うたびに出会う、量ることのできないもの、結果ではなくプロセスこそが、大切なのではないかと思われる。
「心のアート展」は第1回展から、回ごとに応募される作品の質・実に合わせ、独自の標題を創案し、提示してきた。今回、第7回の標題は『境界を越えて:生の原点に還る』。「境界」の和語「さかひ」は「坂合ひ」、坂と坂の行き交わる場所を指している。漢字の「境」も、土地の区切りという意味。「生」の和語「いく」は「息」と同根で、古来、呼吸は生命を意味していた。漢字の「生」は木の芽が芽吹く姿を表している。通時的に見ると、ひとつの生命の持続のなかで呼吸が繰り返されるように、枯れてはまた芽吹く木の芽のように、ひとつひとつの生命の終焉と再生は長い時のなかで繰り返されている。
共時的に見た時、その営みの中には私と共に生きる無数の他者が存在している――。その無数の魂がそれぞれの「生」の道の交わりで境を越えて出逢うということは、ただひとりの短い人生では知り得ることの出来ない、全体としての「生」の集合体と出合うことなのである。
真に「生」を知るということは、様々な境遇を共に生きる人々と出逢うことにある。個体であるひとつの生命を超えて、連綿と繰り返されてゆく全体としての「生」につらなっていくことこそアートという営為の本性である。それこそが「心のアート展」が目指し、且つ試行し続けているコトである。