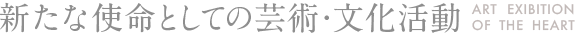私は美術方面の仕事のほかに、音楽教室でリコーダーの講師もやっているのだが、その20人ばかりの生徒のなかにも、もと統合失調症、という人や、もと鬱病だ、という人がいる。これは私がそういう人を選んだとか募集したというわけではなくて、まったくの偶然でそうなったのだが、精神の病、精神障害というものは、日常茶飯事的に、どこにでも「普通に」あるものなのだなあ、ということを強く実感する。当事者の方々にとってはちょっと語弊があるかもしれないが、ほんとうに、「風邪をひく」くらいの感じで、精神的な患いというものは、世の中のどこにでもありうるのかもしれない。
こういうなかで、精神障害者の創作した美術作品の発表ということについて、どういう場合が望ましいと考えられるだろうか。まずひとつは、とくに精神障害者の作品と銘打たずに、普通の作品展あるいは作者の個展のなかで展示される、という場合が考えられる。美術を創作するひとは、その創作動機については誰もさまざまに個別的な事情を抱えているだろうし、そうした事情を誰しもがはっきり明かしながら作品を発表するわけでもない。要は観衆が作品そのものから何を受け取るか、ということなのだから、精神の病というものも、明かすとも明かされずとも、「普通に」作品の背後にありうべきと想像されるひとつの事情として、社会や公衆に受け入れられていくべきだろう。本来的には、精神障害者の方々の作品発表については、こうした在り方が理想的として目指されるべきなのかもしれない。
さて、もうひとつの場合として、この「心のアート展」のように、精神の病を得た人々が集まって作品展を開く、ということがありうるが、このことはどう考えたらいいのだろうか。具体的な理由としては、もちろん、そうした人々はこういう機会でもなければ作品を発表しにくい、ということはあるだろう。だがそのことはいまは措いておくとして、こうしたグループ展の場合、「精神の病を得た人々が創作した作品とはどういうものなのか」「精神障害者の方々が作品を創作するとはどういうことなのか」「精神の病とアートとの関係、精神の病と『表現する』ということの関係とは、いったい何なのか」という問題――そしてそもそも、「芸術の創作と『心』とは、どういう関係にあるのか」、という問題――が、その作品展の重要なテーマとして掲げられる、ということになる。これらのテーマについてより広く深く世間の人に考えてもらい、精神の病ということ、そしてそれと芸術との関係について考えてもらう、ということが、個々の作者の作品を観て、その表現を受け取り、感じ、考える、ということに加えて、展覧会の重要な意義だ、ということになってくるだろう。
精神の病を得たひとの芸術の特徴はなにか、といえば、それはやはり、自らの「心」をひたすら見つめる・凝視する・見つめ直す、というところからくる、「心」の痛みや苦しみや、怒りや葛藤や、喜びや希望や憧れをより深く表現したいという真摯な欲求、それに世間の規範のようなものを問い直す、といった姿勢、が挙げられるのではないだろうか。それらはどれも他にはない表現の強烈に個性的な相貌と、その徹底性の感触を生み出す。今回の「心のアート展」でも、観るひとは、それぞれヴァラエティある「個性」の表現に深くうたれ、そこに喜びを得、あるいは生きる力を与えられるだろう。審査員である私もそうだ。「心のアート展」が貴重なのは、そうした徹底した「個」の表現に出会えること、こそにあるのではないか。
だがそれと同時に、「心のアート展」全体を、個々の人々の表現が結集された、ひとつの集団制作、いわば集団による「壁画」のようなものとしてみることも、可能ではないだろうか。いま私は近現代美術の歴史をみわたしてみて、そこでは思ったほど創作者の「個性」が常に第一に重視されていたわけではなくて、より「社会」との関係性が重視された側面が強かったのではないか、ということを考えてきている。そのことの是非はともかく、「心のアート展」を、個々人の「個」が強く刻み込まれながらも、それらが、精神の病を得た人々の一個の「社会」を形成し、その社会が全体としての表現となって、より大きく広い「社会」に問いかけや呼びかけを行いつつ、大きな「社会」に包摂されようとする、そのようなものとして考えてみることもできるかもしれない。ひとつの開かれた「社会」として、もっと大きな「社会」に向かっているもの、としての、「心のアート展」。そんな観点からも、いまの、そして今後の「心のアート展」をみていきたい、と思っている。