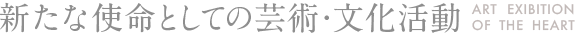今年も私の体の状態が万全でなく、ペースメーカーをつけているのに、不整脈がでたり、胸の痛みに襲われたりする。友人が次々に亡くなっていく。丸谷才一が急逝したと思ったら、安岡章太郎が逝ってしまった。その追悼の文章を書いている最中に、安彦講平先生から原稿の催促の電話があった。ずっと気にはなっていたのだが、前述のごとき体調に加えて、友人の死という避けようもない冷たい風に追われていたのでお許しあれ。
今回の作品審査も平川病院で行われた。抑鬱の心をそのまま絵画に写していくタイプの絵には審査の眼を深く惹かれる。作者のなみなみならぬ苦しみを、深い同情とともに見ていると、作者の苦しみを少しでも慰めてあげたい気になる。これはリアリズム表現の持つ蠱惑的な力である。多くの人に、おのれの苦しみを伝えることによって、その人の病がすこしでも軽くなればいい。そういう祈りを引き出す力のある作品がいくつかあり、本来憂鬱になるところが、作者と一緒に病気にむかっていく勇気を得る。これが絵画表現の不思議な力である。時には、鬱の暗い表現が返って希望の表現になる、私は作者の名前を控えていなかったので、名前をあげることはできないが、暗いトンネルの向こうに幽かな光が見えるような絵画があって、その光まであくまで辿り着こうとする、作者のうちなる力に感心した。
明るいパラソルが乱舞する作品があった。空をパラソルにすがって飛んでいく。これはファンタジーの世界である。現実にはありえないが、夢にはよく出てくる光景なのであろう。文学の世界では、最近ファンタジー流行りである。非現実の希望が大流行りなのだ。ただこういう作品は、どうしてもお互いに似通ったものになり、独創性は薄くなる。
細密な鉛筆画が今回もあった。細かい線が伸びていき、からみあい、対象の意味は分からないが、その混乱が美を醸し出すのは不思議である。私は学生時代に脳病理学の実習に夢中になり、人間の持つ不思議な造形に感嘆した。特に脳の顕微鏡映像を見ていると、人間の心を支えるのは鉛筆画のような無数の脳細胞だと心から思った。心はこの不思議な神経細胞から出てくる。それが何故かは、現代医学では解けない。統合失調症やうつ病とセロトニンとの関係に、研究の進歩を嬉しく読むが、まだほんの一歩を踏み出したばかりで、わからぬことが一杯である。そんなことを思いながら、沢山の鉛筆画を興味を持って鑑賞した。細い鉛筆の線が悪魔の表現になっていたり、不可思議な荒野になったりする。恐ろしいと同時に楽しい。不思議な絵画の列である。
「心のアート」は美しく、また個性を持ってほしい。それが私の第一の願いである。次に、精神の病が脳の神経細胞から紡ぎ出してくる独創である。そういう作品もあった。才能と病が協力して独創を産み出す。
今年の楽しみは花の季節に、フランスからアトリエ・ノン・フェールの作品とスタッフが来訪することである。国際化した「心のアート」が、握手し、お互いに励ましあう。それは、なんと麗しい友情を作りだすことであろう。