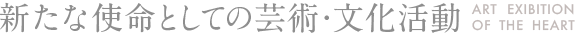そんなにもあなたは待っていた
かなしく白くあかるい死の床で
わたしの手からとった一つのレモンを
あなたのきれいな歯ががりりと噛んだ
トパアズいろの香気が立つ
(高村光太郎「レモン哀歌」一部抜粋)
高村光太郎(詩人・彫刻家:1883-1956)の妻・智恵子(洋画家:1886-1938)のことを、この「レモン哀歌」のフレーズと共に記憶される方は多いのではないでしょうか。この詩が収録された『智恵子抄』(1941年)は、光太郎から智恵子へと手向けられた、美しくも哀しい愛の讃歌と言えるかもしれません。
智恵子は46歳の頃から精神の変調をきたし、転地療養を試みたり、自宅にて光太郎の看病を受けたりしていました(智恵子が心を病むに至った状況については、北川太一氏の「智恵子の場合」をご参照ください)。しかし病勢の悪化は抑えがたく、意思の疎通さえできない狂躁状態が続くようになり、力尽きた光太郎は、智恵子49歳の時、彼女を南品川の「ゼームス坂病院」(現在の品川区南品川)に入院させることを決意します。以降、肺結核によって52歳で亡くなるまで、智恵子はこの病院の15号室で過ごしました。
智恵子が過ごした「ゼームス坂病院」は、1923(大正12)年春、精神科医の斉藤玉男(1880-1972)が独力で開設した神経内科の病院です。斉藤は1906(明治39)年に東京帝国大学医学部を卒業した後、日本における精神医学の創始者・呉秀三(東京帝国大学教授:1865-1932)の精神科教室に学び、その後アメリカ留学を経て、日本医学専門学校(現・日本医科大学)教授や巣鴨病院副院長などを務めました。
斉藤の師である呉は、精神病患者を人道的に処遇することを理念とし、巣鴨病院院長時代には、それまで厳然と行われていた患者の身体拘束を禁止するなど、様々な改革を行いました。呉と斉藤には長く確執もあったようですが、心を病んだ患者に対して人道的な処遇を行わなければならないという使命観や治療理念は、師弟の間に強く受け継がれたものと考えられます。
事実、斉藤が開設した「ゼームス坂病院」は、当時としては極めて異色の病院でした。まだ精神病への治療方法が確立していなかった当時、「精神病院」と言えば、精神病の「治療・療養」を目的とするよりも、むしろ精神病患者の「監禁・拘束」を行う場と言った方がふさわしく、そこに収容された人々の処遇も大変悲惨なものでした。
しかし「ゼームス坂病院」では、患者が自由に外出できる自由開放制がとられ、病室はすべて個室であり、通常の病院には備わっていた「鍵」も「鉄格子」もありませんでした。ただ、このような手厚い看護を行うために、同院の入院費用はかなり高額なものであったようです。
同院に入院した智恵子は、1937(昭和12)年頃から病室で紙絵の制作をはじめています。折り紙からはじまった制作は、その後マニキュア用のハサミを用いての精密な切り絵へと展開していきました。智恵子はいつも病室の決まった場所で紙を選び、時折お辞儀をしたり、独り言をつぶやきながら無心に紙を切り続け、できあがった作品は、見舞いに来た光太郎の他は、医師にも看病についた姪・春子にも見せなかったと言います。
こうして智恵子は15号室の中で、千数百点におよぶ切り絵を制作しました。斉藤医師は治療の一環として、患者たちに手作業を推奨したと言いますが、当時の精神医療の状況からすれば、患者が病室で自由にハサミ(刃物)を持つということ自体、他に類をみない希有な出来事であったと言えるでしょう。
その後、智恵子の切り絵は、光太郎や協力者たちの並々ならぬ尽力によって戦火をまぬがれ、現在にまで受け継がれました。智恵子にとって「切り絵」とは何だったのか。また光太郎にとって智恵子の「切り絵」はどのような存在だったのか。智恵子の死後、光太郎はそのことを象徴的に表す言葉を残しています。
千数百枚に及ぶ此等の切抜絵はすべて智恵子の詩であり、抒情であり、機智であり、生活記録であり、此世への愛の表明である。此を私に見せる時の智恵子の恥ずかしそうなうれしそうな顔が忘れられない。(「智恵子の切抜絵」1939〈昭和14〉年)
智恵子が残した「此世への愛の表明」に是非とも触れてみてください。
参考文献
- 北川太一編『智恵子 その愛と美』二玄社 1997年
- 北川太一『智恵子相聞――生涯と紙絵――(改訂版)』蒼史社 2004年
- 岡田靖雄『日本精神科医療史』医学書院 2002年