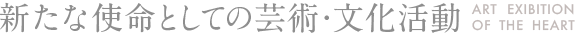権威ある『精神医学事典』にも、かつて精神分裂病と呼ばれていたこの病いの原因は、「遺伝と環境とのあざなえる縄の如き関係の中で発生してくる疾患というしかない」と記されていて、はるか後の新版でもその事情は変わらない。しかしこの世に生を受けた人間に、遺伝と環境を持たない者があり得るだろうか。千変万化の捉えがたい可能性を実現するその表現から、人間のいのちの真実を追い求めようとして続けられて来た人々の果てしない努力は、その来し方、行く末を探る限りない意味を持つ。普通の人間と異常な人間の境界など、実は無いのかもしれない。
錯綜した家系の、時代の波にのったみちのくの俄か作り酒屋、その長女に生まれた智恵子は、自然や手仕事を愛する、運動好きの、機智に富んだ少女だった。しかし、上京して日本女子大学に進み、絵画に熱中し始めた頃の智恵子を初めて知った高村光太郎は、「彼女は異常ではあったが、異状ではなかった」と書く。入籍をかたくなに拒否しながら、アトリエに共に棲むまでの愛の経緯は、光太郎の詩集『智恵子抄』の大きく区切られた前半を見ればいい。アトリエで本を読んでいて光太郎の友人が訪ねて来た時も、ちらりと振り返っただけでそのまま読書を続けていた智恵子のエピソードを、江口渙が伝えている。はるか後になって、『智恵子抄』は徹頭徹尾くるしく悲しい詩集であったと術懐したその後半への導入部である。
油絵具克服への限りない苦悩、父の死、郷里の弟妹たちに次々に降りかかる悲運、実家の破産とその喪失、高村家の長男の入籍しない嫁の立場。そして自殺未遂。すでに日々は異状と呼ばざるを得ない。少しでも安らぎをと願って母のいた九十九里浜に試みた転地も、かえって症状を悪化させ、一年足らずで連れ帰った智恵子はすでにアトリエ療養の域を越える。その智恵子を紙絵制作に導いたのは、斎藤玉男が神経科を標榜するゼームス坂病院の15号室だった。精神病者の入院を主としながら、25部屋ほどのこの小さな病院は、通例に反してすべて開放、鍵なし、窓にも格子がなかった。限りなく色を塗り重ねられる油絵具についに満足しなかった智恵子が、ここで紙という素材の色彩や感触に出会ったことは、なんという幸いだったか。日毎に小さなマニキュア鋏を取り出して紙を切り、貼り重ねる繊細な作業の殆ど唯一の実見者、付添っていた姪の春子がその様子を記録している。
昭和13年10月5日、智恵子は53歳で亡くなった。死因は久しい肺結核だったが、光太郎にのみ見ることを許した紙絵は千数百点に及んだ。紙絵作品の存在を初めて世に示したのは昭和14年2月の雑誌『新風土』であったが、そこで光太郎は「これらがすべて智恵子の詩であり、抒情であり、機智であり、生活記録であり、この世への愛の表明である」と書いた。しかし見るものがその耳に疑いもなく聞くのは、言葉を失った智恵子が光太郎に語りかける刻々の肉声に他ならない。紙絵を知った歌人斎藤茂吉は、打って返すように、そのあるものの、小さきものの命のありようを再現した光太郎の木彫作品との共通性を指摘した。紙絵の中に常に光太郎は共に生き、そのことによって智恵子はあらゆるものに光り輝く命を与え、語りかける声を与えた。
智恵子の紙絵を見るたびに考える。人間の生の蓄積の意味を。昇華と創造される表現の思いがけない抽象性、超常性、純粋性、発現性。そしてそのことに注がれ、しかと見届ける凝視者たちの無私の愛が、いのちの不思議につけ加える、人間の限界を突き貫くその可能性を。