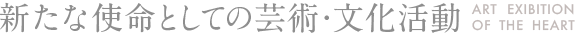この度、東京精神科病院協会の主催で『心のアート展』が開かれる。開催委員の一人である安彦講平さんは、東京足立病院で1968年以来、40年にわたり患者の自由な表現の場〈造形教室〉を続けてこられた。その自由な関係をともにして来たものとして、当院の40年間を振り返ってみたいと考える。
思えば、そこに心を傾けて打ち込んだ労作を出されている人達、あるいは、そこには自分の作品を出されていないが、ひたむきに何かに関わろうとしてきた人達も含めて、共に東京足立病院の改築前の暗い老朽化した精神病棟の中で紙を広げ、自分の思いを描きだした歴史がある。
40年前、当時の当院における病室には何もなく、窓枠は鉄格子で囲まれ、縁のない畳が広く敷き詰められた大部屋で、何のプライバシーも保てず、その大部屋の片隅にうずくまって、いつ出られるか分からない孤独感と不安に包まれていた。そこに皆長くいることになるのだが、そこは各々のやすらぎの場ではなかった。
昭和30年代、精神病棟は全国的に増加の一途をたどっていたが、1958年、当時の厚生省は「治る」見通しが持たれないゆえか、「特殊病院」として「結核、精神科の医師・看護婦を医療法の三分の一でよし。」と位置づけた。ちなみに、その頃よりイギリスでは、「精神科病棟は他科と異なる医療ではいけない。」と、開放化及び精神科病床の削減努力と、精神科病院中心から地域ケアを重視した精神保健医療福祉サービスへの転換が行われはじめていた。過去40年間にわたり欧米先進諸国は、このような改革を国の施策を含めて実施、その結果としての入院資源の低減と地域精神医療福祉の補完が進行されてきたと思う。
一方、我が国では制度改革が遅れ、入院者も先進国の中で一番多く、地域資源も遅れ、日本は欧米に30年は遅れているといわれている。厚生労働省がその世界の趨勢に気づいてないはずはないだろうが、日本人の人権意識の低さ、閉鎖性と相まって、国の制度・対策は遅れ、本格的に改革に着手したのは平成16年9月の「精神保健医療福祉の改革ビジョン」と平成17年公布の「障害者自立支援法」からと言われているが、社会の受け皿は乏しく、「ノーマライゼーション」は言葉だけに終わっている。
このような制度改革の遅れから「困り者」を社会から排除する仕組みは今なお続いており、精神障害者への差別・偏見はその対処の仕方に比例していまだに根深く引きずられている。
過去を振り返れば、その様な差別・偏見の中で、日本各所で精神科病院建設は近隣住民の反対に出会い、苦労の末、都市郊外の田圃の中や山の中に建つことになった。当時の入院風景として、そこに入れられる人は家族から“宜しくお願いします”と言われ、病院も“お引き受けいたします”と入院を受ける。その個々の患者さんにとっては、いつ帰れるのか永遠の別れのような絶望感・寂しさを抱かせられる。入院前の緊張不安の中で家族との衝突があり、家族と少し距離を置いた方がいいよという「治療論」が便利に使われていた時代。
服薬、検温、食事、布団を運び、隣の人と重なるような敷き方で“いたい!”と時に人の足を踏み、それにも馴らされて眠りにつく。昼間は、廊下を「徘徊」したり、部屋の片隅でうずくまるか、横になるしかない。そこにゆっくりしていることが「治療」で、生活の場もなかった。たまに職員付き添いで散歩に出るのだが周りの目の厳しい中、付き添い職員もピリピリし、楽しむより黙々と歩いて帰ってくる。
そんな中、何とか楽しめる場を、と大部屋に机を持ち込み、絵を描こうかと画用紙・クレヨンを用意、女子病棟では編み物を始めたり、買い物に出て食べたいものを作ろうと料理に取り組んで、みながその時間を楽しみに期待するようになり、話し合いの場、コーラス、壁新聞作りなど回を重ね、広がりを持った。うつむいていた人が笑顔を見せ、あるいはすぐに近づけなかったひとも少しずつ手を出し、何かに関わりだした。
そういう動きの中から、“自分たちの表現、作ったものを外に持っていこうよ!”と、当事者で作ったサークルの場で話し合いが始まった。そのサークル「オアシス」が作られるきっかけになったのは“僕の病気って何?”、“病気のことを職員さんだけで話し合うのでなく、一緒に話してよ”と、ある青年から問われた質問が大きな波紋を呼び、話し合う場を作ってきたことになる。1991年初夏、院内のホールで、自分のことを語り、自分の描いた絵を見せ、保護室にいた患者さんも参加して自分の病気について語り始め、ホールに集まった100人近い人達が感動して聞き、ギターを奏でる患者さんにも、外から来られた人達にも、心に残る励みを与えてくれた。もっと輪を広げ、話し合いを町の中で、誰でも参加できるような場を作っていこうよ、と当事者のサークルを中心に胸を膨らませた。
1992年その街の中で〈“癒し”としての自己表現〉の展覧会とギャラリートークを計画し、絵、習字、切り絵などを運び展示し、その建物の前で声を掛けながらビラ配りをした。会場に来てくれた人には、みな自分の絵に託した内なる思いを語り、熱心に聴いてくれる人がいるとみな感動し、満たされる嬉しさを噛み締めていた。そこには、100号の大きな油絵も幾つか出されたが、いつも病院の机の片隅でひっそり描かれたもの等いろいろ持ち込まれ、多くの「病」者のありのままの思いが表されたと言える。その一人ひとりの個々の歴史があり、すでに居なくなっている人もいるが、その場の感動をもとにずっと自分の表現を続けておられる方もいる。
自らの心を込めて描き続けてきた中で多くの作品を表現している人達もいるが、その限られた場、関係の中で充実感を持って向かいながらも“俺の人生なんだったんだ!”と、憤懣やるせなく自分を語る人もいる。その人は、この何年か“仕事をしたい”とハローワークにも行ったりしたが、20代半ばで入院になり、60歳になる現在まで入退院を繰り返し、働きたいと願っても、社会にそんな場はない。やはり、「精神病」と聞くと受け入れてくれるところはない。しかも、自分の絵を見てくれる人を前にして自分の病気のことをありのまま説明する、それはかなりのエネルギーを要するのだが、それは仕事ではない。
続けて表されることが、新たな感動を周りにも抱かせてくれて、それらの積み重ねられた表現の賜物が、今回の『心のアート展』を創り上げている。そこには、展示されていない人達の苦悩の思いも共にあると考えらることだろう。言い換えるならば、何十年に亘る差別・偏見の歴史を歯を食いしばりながら歩み続けた人達、その歩みを共にしてきた多くの同胞の思い・姿をあわせ見て、感じ取っていただければ幸と思います。
2009年1月