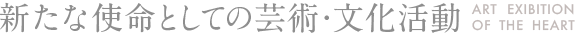「第1回 心のアート展」に出品された作品を見ていくうちに、私の胸に不意に薄幸の詩人村上昭夫の『雁の声』という詩の一節が浮かんできた。
雁の声を聞いた
雁の渡ってゆく声は
あの涯のない宇宙の涯の深さと
おんなじだ
私は治らない病気を持っているから
それで
雁の声が聞こえるのだ
治らない人の病いは
あの涯のない宇宙の深さと
おんなじだ
村上昭夫は『動物哀歌』という一冊の詩集を残して、昭和43年41歳で肺結核のため盛岡市の療養所で亡くなった。
「涯のない宇宙の涯の深さ」とおなじ雁の声は、「涯のない宇宙の涯の深さ」とおなじ「治らない病い」を持っている「私」でなければ、聞くことはできない。
この詩を読むと、人は健康であることが恥ずかしくなる。治らない病いになりたいという誘惑にさえひき込まれていく。
村上昭夫は『病い』という詩で、「病んで光よりも早いものを知った/病んで金剛石よりも固いものを知った/・・・病いはおそらく/一千億光年以上の/一つの宇宙なのだ」とも歌っている。
肺結核と精神病であったムンクは、「これらの虚弱さを私はそのまま残しておきたいと思う。それは私自身の一部でさえあるのだから。・・・私は病いを遠ざけようとは思わない。自分の芸術で私がどんなに多く病いに負うていることか」(鈴木正明『ムンク』)と語っている。
ムンクの『病める子』や『春』のいずれの画面でも、病める少女の面差しの透き通るような蒼白さは、たんに病的な色というより、霊的ともいえる光を放っている。この光は病者のみが放つ光であり、病者のみに見える光でもある。病者の持つプリズムだけを通して放つ光である。
詩集『動物哀歌』が晩翠賞とH氏賞を受賞したとき、村上昭夫は「ほんとうにたよれるものはなにか。宗教とか、物を作るとか、いろいろなものが考えられるでしょうが、私の場合ですと、やはり今までどおり『死』という暗く悲しく、つらい色をした、もっと強度の眼鏡をかけなおして、ふたたび耐えがたい旅に出るほかないのです」(「岩手日報」)と語っている。
私はこの「心のアート展」に向けて、「あなたの声なき声、呟き」、ため息、独り言、そして魂の叫び、・・・を聞きたい」と呼びかけた。
いま、ここに集まった作品の一つ一つからは、期待通りの叫びが聞こえてくる。それは「涯のない宇宙の涯の深さ」から響いてくる声である。
それはときに戦慄的に、ときに啓示的に聞こえてくるが、やがて、これらの作品たちはたがいに交響し合い生命の讃歌を奏でていくのである。