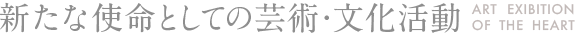1968年以来、東京足立病院〜丘の上病院〜武蔵野中央病院〜平川病院で絵を中心とした表現活動の場〈造形教室〉を創設し、40年。東京足立病院、平川病院で現在も継続。1992年から「“癒し”としての自己表現展」を開催。以来、毎年続け、今年6月、第16回展を迎える。
〈造形教室〉に集う殆どの人は絵が好きだったという人ではない、そして美術専門の教育を受けたこともない人たちだ。まさに“病いとの出会い、絵との出会い、人との出会い”というべきだろう。いつも思う。もし、私が絵ではなく、音楽を愛好するもの、歌や演奏が専門だったなら、このアトリエは一つのスタジオになっていただろう。演劇や舞踏などが専門だったら、身体表現の舞台となり、詩や小説を書く人間だったら、文章表現、朗読の場になっていただろう。形あるものの創作活動が、自らを“癒し”支える場と関係という無形の“作品”を創り、織りなす活動でもある。
精神科病院内でそれぞれが表現する主体となって、“教育”や“療法”ではない自由な表現をしていくために、まず、その地盤作りから始めた。場を作り、関係を作るという、もう一つの土壌作り=耕作(カルチャー)を同時に進めていかなければならない。手を休めたり、気を抜いたりすればたちまち雑草がはびこり、また掘り返し、土壌をならし、思いがけない難関と出会い、それがまた転機となって新たな境地が拓かれていった。その終わりのない作業がなぜ、人間は芸術を必要としているか、表現することの意味、芸術の存在理由を考え続け、私自身の心身を鍛錬し、心の糧になっていた。
その時その人のかけがえのない自己表現を通した創造の場が、作品に表れていない水面下の、波瀾万丈の過程の中で営まれてきた。「ここは自分たちにとって他に代えられない必要な場」として通いつづけ、表現し、語り合ってきたたくさんの人たちこそ、“癒し”としての自己表現の方法を血肉化し、その存在理由を保証してきた。
一般には絵は視覚的な表象、枠に囲まれた二次元のイメージの世界とされている。しかし、結果として現れたものは一つの現象、一断面。外観からは容易に見ることのできない、窺い知ることのできない水面下の、様々な問題が底在している。そして、ものを作っていくことが心身の浄化、蘇生作業であり、自分自身の内面と向き合い、見つめ直す契機、プロセスでもある。絵は言葉では容易に表わせない、他者の前では伝え難い、その時々の感情、深層を表し、そして見る側の視点や心の動きによってさまざまに枠を広げ、奥行きを深めていく。時間的、四次元的表現の世界である。ときには描いた人自身も意図しなかったイメージやメッセージを感じとる、見る人自身の問題が喚起される、といった双方向からのダイナミックな関係、交感が生み出される。既成の知識や趣味趣向にとらわれて、固定された位置から見ているだけでは、絵は、枠の中に収まった静止画面にとどまる。絵を「目で触るように、心で聴くように」向き合うとき、絵と見る側の仕切りが取り払われ、インターアクションが働いていく。
苦難の中で「心の杖として」生み出された作品は、作者自身を、見る人を、そして困難な現代を生きる全ての人の生命の深淵を映す「鏡」、といえよう。
応募作品の原画を前にして、真っ先に「障害者の描く絵」「アート・セラピー」などの既成の知識、先入観がくつがえされ、敷居、段差は取り払われた。ダイレクトに訴えかけられてくる作品群を選りすぐり、展示した。
苦悩や病いを抱え、窮境の中から生み出された作品こそ、それぞれが自分自身に向き合い、困難な現代社会に問題を投げかける表現ではないか。
「心のアート展―生命からのこもれ日」第一回の創刊、準備展を少しでも多くの人たちにご覧いただき、原画と向き合い、有形無形の問いかけ合う〈場〉になれば、と心から思う。