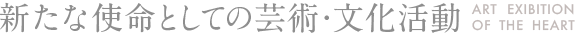安彦講平(〈造形教室〉主宰)展覧会の会期中、その日その時に参集した方たちと、ギャラリートーク、座談会を随時、行ってきました。今日も、親密な方たちが来られています。それぞれ、語りたいことを語り合うというような座にしたいと思います。
本日はこの「心のアート展」に繋がる「“癒し”としての自己表現展」や精神科病院内での芸術活動に長年一緒に協働してきた荒川幸生先生もいらしています。
それから東京足立病院で出品者の一人と深い関わりを続けてきて、今、浅草のクリニックでの診療所をやっておられる伊波真理雄先生も来館されました。それから今年の5月、京都造形芸術大学で「臨“生”のアート」という展覧会を開催しました。「臨“生”」とは病に臥している人に臨むのではなくて、「生きる、全体に臨む」という意味を込めて「臨“生”のアート」としました。その展覧会を提案、実行された藤澤三佳先生も来られています。
また、平川病院〈造形教室〉に10年来通い続けて記録映画をずっと撮り続けているドキュメンタリーカメラマンの高橋愼二さんも来られています。今回の〈特集展示〉のために、名倉要造さんの大森の自宅でインタビューした映像もあります。
様々な形で、それぞれの専門領域、立場からこの展覧会と深いつながりがあり、関心を持っておられる方が多いように思います。では、最初にどなたか。荒川先生、お話しいただけますか。

荒川幸生(荒川メンタルクリニック・精神科医)僕は今、八王子の駅前のクリニックで毎週、診療しておりますが、安彦先生が八王子の丘の上病院というところで20数年前ですか、〈造形教室〉をやっていた時に、私は医者として関わったわけですが、当時は本木さん(本展出品者)とかがいらいして、昔からの、何て言うんでしょうか、仲間ですよね。そういう感じの仲間たちが長年続けてこられたことが、このような大きな展覧会に作品を出されている。最初は八王子の図書館で、周囲の皆さんに心を病む患者さんたちの作品を見ていただこう、少し開かれた活動をしよう、ということで始まったわけですが、それがこのように東京都内の民間病院団体が主催する展覧会となり、大きな広がりを持ってきたということは、僕としては大変感慨深いです。
それにも増して、今、こころを病んでいる方が大変多くなってきておりますが、市民の皆さんが非常に関心を持ってこのような展覧会に来ていただけるし、プロのアーティストの展覧会とはちょっと違う、非常に迫力のある、立川先生(北里大学名誉教授・心のアート展審査員)が言っている、まさに「魂の叫び」。我々の立っている足元をむしろ逆に照射するような作品が非常に多いのではないか、というふうに感じました。
こちらの伊波先生が『不完全でいいじゃないか!』(講談社文庫)というような本を書かれておられますが、本当に僕もそう思います。病気であろうとなかろうと、同じ、何とかやっていけるような、そういう社会であったらよろしいのかなと思っています。
安彦続いて、藤澤先生はいかがでしょうか。

藤澤三佳(京都造形芸術大学)今年の5月に京都造形芸術大学の「ギャラリー・オーブ」で〈造形教室〉の展覧会を開催させて頂きました。学生が800人くらい来て、すごい反響で、その感想文を回収したのですが、その中で印象深かったのは、ギャラリートークの時に、佐藤さん(本展にも出品)や何人かの方が、「生きていてよかった。この〈造形教室〉がなかったら生きていけなかっただろう」ということをおっしゃったんです。それに対して、私もすごく反応しましたが、学生の中にもそういう病気だったり、何か悩んでいる子が非常に多いので、「今日も生きていてよかった」という、同じような共鳴をしていることでした。
それから、「ここに来る前は、精神病院ということで、暗い絵が多いんじゃないかと思っていたけれども、見たらものすごくエネルギーに溢れていて、生きたいという叫びとを感じた」という感想もありました。また、「めまいがする」「動悸がする」とか、「ものすごく自分の存在を揺るがされた」というような感想も5、6人ありました。そこまでドキドキしたりする絵はなかなかないと思います。
本当に自分の存在を、見ている人の存在を揺るがされるほどの衝撃感を与える絵。安彦先生がおっしゃるように、単に癒されるとかそういう受け身な姿勢ではなくて、表現の主体となって、人間の深いところまで感じさせてくれる、そのように鑑賞した感想文が多くありました。今、荒川先生がおっしゃいましたが、病気を治すとか、病気になったらいけないとか、そういうことではなくて、病気でもいいんじゃないか、みたいな、そういうところにすごく共感を得ました。
最近ではアウトサイダーアートとか、アール・ブリュットとかいう、アートの中の異端、障害を標榜する「アート」の流行化現象が起こっていますが、こちらの展覧会は、治療とかアウトサイダーアートではなくて、普通に皆さんたちがお話しをしている、今日の座談会のような場がとても画期的というか。本当は当然のことなのでしょうが、いまは忘れられてしまっていて、医療やアートが何か違った方向に行っているのではないかと思います。ここにいる皆さんには当然のことなんでしょうけど、普通に表現してお話しできて、こういう時間が持てることが画期的だし、私にはありがたいと思います。
今日は京都から新幹線で来ましたが、先程の紙芝居がすばらしかったですし、来てよかったなとしみじみと思いました。これがアートの力だなと思いました。
安彦ありがとうございます。それでは伊波先生をご紹介します。先生は沖縄の出身で、沖縄にいた時から関わってきた青年がいました。その青年が、伊波先生を追いかけるようにして島(沖縄)からこちらに来て、そして、〈造形教室〉と出会い、絵を描き始め、現在へと(本展出品へと)つながっています。
また、伊波先生が東京足立病院に勤務していた頃、〈造形教室〉にやってきて自宅の表札か何かを造っていたら、一緒に参加している患者さんから、「あなたは何年ぐらいここに入院しているんですか?」と聞かれて、「まあ、○○年です」と答えたり、白衣を着ての1対1で診察というだけではなく、病院の中の時空間で一緒になって患者さんと過ごすという関係をつくっていた。『不完全でいいじゃないか!』という本の中には、伊波先生の出自の経緯から、沖縄の青年との出会いや東京足立病院での再会のことなどが書いてあります。機会があったらお読みになってください。では、伊波先生、お願いします。

伊波真理雄(雷門メンタルクリニック・精神科医)ご紹介ありがとうございます。沖縄で30年生きていて、生まれた場所がハンセン病の人たちが隔離されている島でした。父親がそこで働いていたので、そこで生まれて、沖縄で30歳まで生活をしていて、私は沖縄でずっと生活する予定だったんですけど、ダルクという薬物依存の職員さんが、研修中に私を覚醒剤中毒だと思ったらしく、東京で一緒に戦わないかと誘っていただいたのがきっかけで、今から18年ぐらい前に東京に出てきて、そこから安彦先生や荒川先生との出会いもあり、お付き合いさせていただいています。
先ほど安彦先生がちょっと触れられた青年、森さんという患者さんについてなんですけど、向こうに3点、大きな100号の絵があるんですけど、彼は、私が琉球大学という沖縄の病院で研修医を始めた時に分裂病という診断を受けた最初の患者さんです。彼はまだ学生服を着ていて、父親に対して暴力的な行動に出たということで入院になり、私が担当となりました。研修医なので、先輩に教えてもらいながら治療者として関わっていくのですが、最初は白衣を着て、できるだけ彼を自分たちのように戻してやろうみたいな、そういう肩に力の入った治療をやっていたように思います。
彼とは3カ月ぐらい、入院生活をお付き合いさせてもらい、その後、外来で診たりしていましたが、私はそのあとダルクとの出会いがあって、沖縄を離れて東京に出てきたので、もう彼のことはすっかり忘れていたんです。ところが、私が東京足立病院で薬物依存の人のお手伝いをしていた時に、「今から入院するから待っていてくれ」と突然、電話がかかってきた。それがまた彼との2度目の出会いで、もともと彼も別の目的だったんでしょうけど東京に出てきて、また発症してしまって、琉球大学に電話したら、僕が東京にいるということを誰かが教えたらしいんですね。それでかけてきたということなんですけど、まあ、私も医者のふりをして治療をしていたみたいな感じがしたので自信も全然なかったですし、僕が関わるようになってよくなったようにあまり思えなかったので、自分としては最初に電話がかかってきて、彼が次の日病院に現れた時は嬉しくはなかったですね。
治療が始まったのですが、東京足立病院は700人ぐらい入院するベッドがある大きな病院でして、彼はいろいろな病棟でトラブルを起こしては各病棟から追い出される。そこのナースたちが、もう彼を置いておけないと言っては追い出される。大体7、8カ所ぐらいの病棟を点々としていたので、どうしたらこの人は、人とうまくやれるんだろうなと思っていました。
そんな時に彼が唯一、安彦先生担当の〈造形教室〉で絵を描いている時だけは、穏やかな感じがすると思いました。そして私も、東京足立病院という場所にこういうスポットがあるんだと魅力を感じました。
私は薬物依存の人のリハビリを手伝う時に絵を少しやりましたが、そこから少しずつ、患者さんが描く絵とか、そういういろいろなパフォーマンスの世界にちょっと魅力を感じるようになりまして、いまだにそれが続いているわけです。
こういう場所に来て、何を言ったらいいのかよくわからないのですが、「魅力」という言葉が一体どういうもので構成されているのか、それについてよく考えます。実力とか、財力とか、いろいろなパワーというものがあると思いますが、こういう場所、特に安彦先生が関わるこのグループには独特の魅力があるのです。先ほど別な先生がおっしゃったように、商売っけとか、治療とか、そういう堅苦しいものから離れて、「おまえはここにいていいんだよ」みたいな、何かそのような、むしろ医者として関わろうとしている自分が、その役割から解放されるような、そんな解放感を感じるのが好きで参加するようにしています。
最初は白衣を着て肩ひじ張ってやっていた自分が、だんだん安彦先生や森くんのような患者さんとの出会いがあって変わっていきました。僕は、森くんが入院中に、彼が急に「墓参りしたい」と言うから、困ったなと思って、おまえのお墓はどこにあるんだと聞いたら、「沖縄」って言うんですよね。入院中に沖縄に墓参りは難しいだろうなと思ったんだけど、やってみようと思って、僕と一緒に沖縄に行って、僕の友人の家に泊まって、一緒に酒を飲みながら、「このことはナースに言うなよ」という感じで、楽しい3日間を過ごしました。彼が「薬を飲まなくていいですか」とか言うから、「いや、それは飲んでおいてもらわないと困る」とか、医者に戻ろうとする中途半端な自分を楽しめたんですけどね。
おばあさんのお墓にみんなで手を合わせてからは、彼との関係がずいぶん変わった気がします。そういうものを、何か治療的に説明するという能力は僕にはないんですね。「そういうことをした」、「その時に何かを感じた」ということぐらいは言えるのですけど、そのあと何かが変わったような気もするが、それが何だったのかと言われると、よくわからないですね。
すみません、まとまりのない話しで。僕の話しはこれで終わります。
安彦ありがとうございます。いつも出会うと新鮮な思いがしますね。
この「心のアート展」は、東京精神科病院協会の主催で都内の施設からの公募で開催しています。第1回目展から少しずつこの展覧会の意図、内容に関心や広がりが出てきて、先ほどから言っている、障害者アートとか、アウトサイダーアートとか、あるいはアートセラピーという枠組みを超えて共感した人達が、この展覧会に自分の作品を出品したり参加することによって、自分の内面の問題を表現していくきっかけになっていけば、と思っています。そういう意味で、今回、何人かの現役の画家の方たちも出品して、田部井さんのような大きな(150号の)日本画の作品も展示させていただきました。
それでは、次に田部井さんから、画家としての生活から重篤な病に遭遇して、それ以降の絵の取り組みについて、お話ししてもらえたらと思います。

田部井月四(日本画家)私は田部井月四といいまして、日本画を描いています。日本画というのはどういうイメージを皆さん持たれていますか。大体の方が古風な美人画や水墨画、山水画というイメージだと思います。しかし、現代の日本画というのは、日本画材を使って絵を表現するというものに変わっています。
私は多摩美術大学という前衛的な傾向の美術を喜ぶ大学に入りました。ずっと創作活動を続けてきて、団体展という枠組みの中で展覧会をやり、そこからなんとか有名になって絵を売っていこうという、「職業としての画家」というものを目指してやっていましたが、ちょうど10年前に脳腫瘍になりました。5センチ以上の脳腫瘍で、それを摘出した時の後遺症で体が動かなくなってしまいました。
(今回出品した)一番左の絵は、自分が全然記憶のない2週間ぐらいの時に、アフリカの川をさかのぼって泳いでいたという記憶がなぜかありまして、それを絵にしたものです。その時にはよくわからなかったのですが、この「心のアート展」の会場で皆さんの絵を見ながらいろいろ思い出している中で、ああ、そういうことを、皆さんもいろいろ考えながら描いているんだなというのを人と話していくうちに、今、(ここに出展することで)自分の作品のつくり方に大きな変化があったと気がつきました。やっぱり内的な必然というものを大事にしていくというのが、ここの皆さんの取り組んでいる姿だなというのを思いました。
大学では創作活動というと、テーマとか、画題とか、そういうところから始めます。画材をどうするか、画面をどういうふうにするかというところからまず入って、いわゆる技術のほうから入ってしまうのですが、心のアート展では絵を描くんだという意思のところから入っていくというのを感じました。
安彦先生とは、新聞に掲載された安彦先生の記事を見て先生のところに行きたいと電話したら、どうぞ、どうぞということで、見も知らずの私を病院内のアトリエに入れていただきました。正確には行かせていいただいたのですが、その時にとてもよい出会いがありました。それは、アトリエで本当に原点的な絵を描くという姿を見せていただいたことです。そして、これが絵の原点なんだな、という感じで安彦先生のアトリエをはじめ、いろいろなところへ通うようになりました。それがご縁で、今回の展覧会で作品を一緒に並べてみないか、というお話をいただきました。私は技術とか、何かそういう裏づけでやるようなものでないところで展示したいと思っていたものですから、今回、出品させていただいて、すごくいい体験をさせてもらっています。
皆さんの中に入って、「ああ、絵を描くということはこういうことだったのか」ということを、今すごく感じていまして、観に来る私の画家の友達も、皆さんいろいろとご活躍しているんですけど、そのことに非常に賛同しています。やっぱり3・11がありまして、自分の中のエネルギーを出していくということはこういうことかというような、そういう思いを皆さんしているようです。ですから、何か今、ここにいられることが非常に幸せで、いい体験をさせていただいていると思っています。
安彦3点の絵の一番左側は150号の大きな絵ですが、あれは本当に断片、破片のつなぎ合わせであのような絵になっているんですね。それも田部井さんの病気の直後の体験が刻まれていると思います。
もう一人方は、高橋愼二さん。またこれも一つの出会いで、平川病院のアトリエに延べ14年ぐらい通われています。最初は自分の映画作品を撮るとか、取材するというようなことではなくて、自分にはこういう場が必要だということでずっと通い続けてこられたようですが、いつの間にかみんなからカメラで撮ってもらっても構わないよと言われた。そういう自然な流れの中でできた映画が『心の杖として鏡として』です。最初は1時間の内容でしたが、2008年にフランスの映画祭に出品することになって、あらためて編集して1時間20分の『破片のきらめき −心の杖として鏡として』という映画ができあがりました。今、いろいろなところで上映され、来場された人たちとトークを行うなど「生」な交流、交感が続けられています。では、高橋さんにお話をいただきたいと思います。

高橋愼二(ドキュメンタリーカメラマン)高橋です。この間まで入院していて頭がぼうっとしています。入院というのは、頸椎をちょっと削ったりと大変な手術でしたが、本人は全身麻酔で全然わからない状態でした。(笑)
さて、今年は日本にとってとにかくすごい年ですね。あの3・11というのは、地震、津波もありますが、原発の問題。これで、僕は日本人の一人ひとりがどう対応するか、「行動する、しない」ではなく、どう考えるかということが問われていると思うのです。
この間、大江健三郎さんが明治公園でやっていたデモに何万人か集まったと聞きました。しかも集まった人は一般の主婦とか、今までデモと全く関係ない人たちがほとんど。このようなかたちで日本がどんどん変わってきた。だけれども、昨日たまたまNHKで夜中の2時過ぎまでやっていた、これは第2部で、第1部もまた、何日か前の深夜にやっていたのですが、日本が原発に突き進んでいく過程というものを、NHKが非常に丹念に、相当昔から歴史を描いたものでした。それを見ていて、とにかく思ったのは、「この人たち大丈夫なのかな」ということです。日本の政財界のほとんどトップの人たちが、今見るととんでもないことを平気で言っているんです。それはこと原発に限らず、日本のあらゆる部分でそうなのです。
僕はよく思うのですが、いわゆる「知識人」は一生懸命勉強して、東大とか京大とかで知識を重ねて、自分の立場をどんどん上に上げていきます。世間で言う出世ですが、そういうところに行った人は何かどこかで人間が変わっちゃうんじゃないか、何かを置き忘れて行っちゃうんじゃないか、という気がするのです。でなければ平然とあのような、昨日テレビで言っていたような発言はできないはずですから。
この空間にいろいろな絵が飾ってあって、その一つ一つを見ていくと、全く違う感性というか、人間の本当に純粋無垢な発想から出たイメージをそのまま描いている。そういうものが今の社会では何か失われていて、逆にこういうパワーが、そういう人たちを凌駕するようなかたちで、よく安彦先生が「逆照射」と言いますが、こういう力を世間に発表して、どんどんアピールしていかなくてはいけないんじゃないか。僕が撮った映画もそんなような意味を込めてつくっているのですが。まあ、そんなことを感じています。
安彦どうもありがとうございました。今、ちょうど建築家の橋本さんが来られました。東京足立病院が古い収容施設のような建物を新館に全面的に建て替えた時に、病院という構造や環境をもっと斬新にしようということで、壁画やステンドグラスを取り入れたりと、設計図面の時から僕も一緒に参考意見を交わしながらやってこられた方です。7階建ての東京足立病院の建築の真正面の二つの壁面に『輪廻転生』があります。朝日と夕日という、8メートルぐらいの大画面です。僕が病院アートということで、単なる豪華であるとか、清潔とか、明るいとかいうのでなく、本当にそこで治療、保養のために24時間過ごす患者さんにとっては勿論、多忙な厳しい労働を強いられている医療者の病院内日常にとっても何か意味がある内容、構造にしようということで考えられたものです。では橋本さん、お願いします。

橋本(建築家)橋本といいます。建築設計を生業としている者でして、東京足立病院とは35年ぐらいお付き合いをさせていただいています。現在、東京足立病院に残っている8棟ぐらいに関わってきました。私が設計をさせていただいて、途中の段階から安彦先生にヒーリングアートというものを少しずつお教えいただきながら採り入れていった経緯があります。
先ほど先生がおっしゃっていたその壁画というのは、平成8年に完成した建物の壁面に、夜明けの金星と落日の夕陽をモチーフにした先生のデザインをそのままガラスモザイクアートにして壁につくったものです。今見ても決して色あせることなく、壁に燦然とそのままのかたちで残っているものですから、今でも行くたびに見ますけれども、それと同じようなアートを一つ一つ取り入れながら、皆さんのお力になれればと思っています。
安彦ありがとうございました。いろいろな方にご指名でお話していただきました。わずかではありますが、残り時間は質問、ご意見や感想等をお願いします。
司会どうでしょうか。今の話を受けてでもいいですし、先ほどのギャラリートークで作者の方が語ったことについてでもいいです。単純に展覧会を見ての感想ですとか、こういう展覧会活動についての感想ですとか、意見とか何でも結構です。ざっくばらんに話しができたらいいな思うのですが。どなたでも発言していただいて結構です。どうでしょうか。こういうのは一番最初の人が緊張するのですが、どうでしょう。どなたか口火を切っていただけますか・・・はい、質問をお願いします。
アナン(大学講師)アナンと申します。イギリスから参りました。誰でもいいのですが、みんなの前で自分がつくったアートを見せるとか、紹介するとか、どういう感じですか。
司会どなたにしましょうか。では、何人かに聞いてみましょう。自分が描いたり造ったりした作品を、こういう公共の場でみんなに観てもらうということがどのような感じかということについて発言いただけますか。
江中裕子(出品者)そうですね。私は手で紙を一枚一枚、ちぎって貼っていって、それがどんなことになるのだろうとは思わないで、小さな部分がどんどん積み重なって大きな絵になって、それをこういう場で見てもらって、共感してもらったり、触れられてみたりと、いろいろなことで人間関係までつながっていくということに、生命の力というか、何かそういうものを感じています。どんな小さなものでも生命力って必要なんだなとか、こういうふうにいっぱい展示されると、1点だけでもたくさんでもそうですけど、命とか魂の積み重ねみたいな・・・。そういうものが見る人とかに伝わっていくのではないかなと思っています。
安彦本木さんはどうですか。先ほどのギャラリートークでも「手を差し伸べる」というようなことがあったけれども・・・。

本木健(出品者)絵を展示するというのは、20回近くになるんですけど、正直、毎回緊張しています。最初は、自分の絵を説明するのに精いっぱいで、しゃべったことは何も覚えていないのですが、だんだんそれが続いているうちに、これは一つの訓練、トレーニングじゃないかと思えてきました。人前でしゃべることのトレーニング。それで自分が話ながら考えているのです。結構、しゃべりながら自分で自分を発見しているのです。意外と普段考えていることを、ここでしゃべって思いついたりしたこともあったりして。それ以外にも、ああそうだったんだと自分で気づくこともあります。
それでだんだん回を重ねていくと、聞いていらっしゃる方が何を求めているのかとか、そういうことに少し余裕が出てくる。聞きたいことは何かなとか、そういうことを考えて、なるべく自分ができる範囲でお返ししたいなというところです。
それでも今日もかなり緊張しています。さっきもギャラリートークで少し話したのですが、自分の作品を展示する、そういう機会を与えてもらえること、これこそ高橋さんがおっしゃったように、発信すること。こちらから発信することをうまく伝えられればいいなと変わっていった。だから毎回少しずつトレーニングしながら、そういうことをしゃべりながら考えさせてもらっているところがあります。
司会他の方はどうですか。自分の絵を展示して、人に見てもらうというのは。
石澤孝幸(出品者)そうですね。展示しても自分の絵を見てもらえなかったり、素通りされてしまうことが多かったけど、中にはじっと見てくれている人もいるし。見てもらえることはすごく嬉しいです。
安彦では、大谷さんも。
大谷祐人(紙芝居作家)今回、ここに作品は飾っていなくて、今日は紙芝居をさせていただいたんですが、僕も絵を、20歳ぐらいから自己流に描いたりし始めました。それまで絵がすごく苦手で、自己表現というのが大嫌いというか、そういう子どもだったのですが、いつの間にか絵を描いたら見せなくちゃ気が済まなくなっていきました。表現して見せるこということは、多分、自分の中では日記というか、日記なんだけれど見せなくちゃならないものになってしまった。先ほどのお話を聞いて、「内なる動機」というか、そういうものから描いているのかなと自分で思ったりしました。そうすると、やはり人に見せるというのは、自分を知ってもらうことであったり、何かをさらけ出すものなのかなと思っています。
僕はちょっと絵を習ったことがあって、習作ということで絵を描かされました。でも、「習作」という言葉がよくわからなかったのです。習作というのは、つまり仮で描くということだと思うのですが、「絵って仮で描くものなのか」「描いたものは作品じゃないのか」と思ってきて、描いたものは全部が作品なのに、何で習作をわざわざ描くんだろうというのがすごく疑問となりました。もしかしたらまだ考えが足りないのかもしれませんが、いまだに習作って何だろうと思ったりしています。
司会ありがとうございます。では、ほかにどなたか発言される方は・・・では、お願いします。

麻生佳津子(医師)私は田部井さんの主治医をしていたことがあります。それで、今日、ご案内いただきました。まず、私は絵が全然わかりません。今まで田部井さんからあちこちの展覧会に、手伝ってほしいと言われて参加させていただいたことはあるんですけど、今日は入った途端に、涙が出て仕方がないのです。(涙)
これは「何だろう」と思って。皆さん本当に何かをつくりだしたいとか、描きたいとか、心底から出てくるエネルギーを私は今日、本当に感じました。
ちょうどこの場に入ってきたら、お名前がちょっとわかりませんが、あちらの先生が患者さんと一緒に沖縄まで墓参りをされたというお話をされているところでした。一緒に墓参される先生なんて、なかなかおられませんよ。
だから、これこそ本当の医療者がこの中におられるのではないかなということで、もう本当に今日は温かい気持ちをたくさん頂戴しましたし、これからもこういう「こころの底から湧き出るエネルギー」を皆さんに表現していただくと、日本は変わるんじゃないかと私は思っております。今日は本当に、来させていただいた恩で、僭越なんですけれど、感想を述べさせていただきました。麻生佳津子と申します。
司会ありがとうございました。私たちもそのように言っていただいて本当に嬉しいです。1回目展、2回目展と池袋の東京芸術劇場という会場で開催し、今回の3回目展は初めてここの会場(アーツ千代田3331)で開催しました。が、実は思っていたほど人の入りが少なくて、今回はちょっと「困ったな」と思っていました。でも、やはり人数ではないと思いました。こうして作品を見て感じていただいて、このようなご意見をいただけると、開催している側としてもとても励みになります。ありがとうございます。
麻生また来年もどうぞご案内ください。来させていただきたいと思います。
司会はい。是非、よろしくお願いします。では、ほかに意見がある方。感想などもお願いします。
西川直子(茨城県大子町自立訓練事務所)初めまして。西川直子と申します。私は今のご意見と同じような意見を持ったので、ぜひ伝えたいなと思っています。私は、アートセラピストという肩書きを持っていて、今、精神科病院の関連施設におりますが、私がアートというものを、癒しというか、それを命として捉えていくということを意識したのは、今から14年前です。
私は外国人の医療相談の裏方役で、在日の人でビザがなかったりとか、困っている人たちのために、黒子になって手伝いをしていましたが、言葉が通じなくて悩んでいる人がたくさんいて、言葉以外でコミュニケーションをとりたいなと思った時に、アートセラピーという言葉をたまたま見つけました。私にはどこでどう学ぶかというのがわからなかったのですが、たまたま知り合いのイギリス人とイギリスへ行くことになって、アートセラピーというのが学べるから、そこでやってみよう、と勉強して帰ってきました。
帰国してから、病院の中でアートセラピストという形で正職員として働いています。今年で3年目に入りますが、実は今スランプに陥っていて、やはり私はアートセラピーではなくて、こういう自己表現が本当はやりたかったんだって思いました。(涙)切り口を変えて・・・、少しずつ表現を始めたところです。いつか私もこのような感じで、自由に生きていく気持ちを伝えられる創作や造形の支援をやりたいなと思います。
何か今までのお話を聞いていたら、いろいろお世話になった人や関係した人がでてきたので、ぜひこの話を伝えておきたいと思いました。本当に素敵なアート展で、毎回楽しみにしています。これからも皆さんのアートを楽しみにしております。
司会ありがとうございます。ほかにどなたかございますか。どうでしょうか・・・、僕、さっきからちょっと(風貌が)気になっていたんですけど、お願いできますか。

横山(大山田ノンフェール)横山と申します。栃木にあります「大山田ノンフェール・くらねぇ」というところに関わっています。大山田ノンフェールは廃校になった校舎を利用し、地域生活相互支援活動をしているところです。
その校舎の壁面に、ここにいる本木さんが壁画を描かれていて、その絵がとても明るいピンクを基調にした、今回の絵とは全然違ったイメージなので、幾つかのことを聞きたいなと思っています。例えば、以前に貝殻に傷をつけた絵がありましたが、あれは要するに折り合いをつけられないということで考える時に、今回の出品作品の『慄きながら手を携えようとする』というのは、ある意味では折り合いが少しつくようになったという風にとってもいいのか、そこら辺がちょっとお尋ねしたかったところなんです。
それから、もう一つ。精神科医療の現場のお医者さんたちがいらっしゃいますので、例えば、これは伊波先生がご専門ですが、依存症の世界では「変えられないものは受け入れる」、「変えられるものは変える」という考えがありますが、それは折り合いをつけることが癒しになっていくのか、それとも折り合いをつけられないものを、折り合いをつけられないまま抱えていくことが癒しなっていくのか、そこら辺が非常に気になっておりまして、本木さんと伊波先生に何かお考えを聞ければと思っております。ありがとうございます。
本木最近思うに、長年描き続けてきましたが、今、目の前にあるこのキャンバスをどういうふうにするかということばかり考えてきたんですけど、家にいると全然だめなんですね。アトリエに行って描いて、その描いていることよりも「何をするか」、そこを考えていること自体でどんどん毎年発表していって、もうそれで病気とかそういうことはどうでもよくなると言ったらおかしいのですが、むしろそれよりも僕は人間的に深くなったことの喜びが大きいです。
病気のことをそんなにこだわって考えなくなりました。結論めいたことを言うと、うまく言葉が合っているかどうかわかりませんが、病気にこだわるよりも、むしろ創作の喜び、そちらのほうが大きくなっていって、最近はあまり病気のことは言いません。荒川先生にちょっと眠れないという時はありますが。
学校の校舎のピンクの絵というのは、あそこの壁面がやっぱり陽が差して、だんだんグラデーションになっていくんですね。ピンクでだんだんこうなって。だからそれは、その場にふさわしいものを描こうということなんです。僕はもともとそういうパステルカラーが好きなのですが、自分の絵として、ああいう風に描いていって深まっていくというのは、すごく気持ちがいいんです。何と言うか、本当に不思議な気持ちですが、自分に裏づけができたというふうな感じもします。
伊波先ほどおっしゃったのは、お祈りの内容ですね。「神様、私にお与えください。自分に変えられないものを受け入れる落ち着きを。変えられるものは変えていく勇気を。そして、その二つを見分ける賢さを」という、もっと原文は長いらしいんですけど、日本では「平安の祈り」と言っています。あと、アメリカで始まったAAの会場では、“The Serenity Prayer”という名前で紹介されています。みんなでこうやって車座に集まって自分の体験談を話したあと、みんなで肩を組んだり手をつなぎ合ったりして、こういう祈りを唱えたり、ミーティングをします。こういう会場で聞けるとは思わなかったのでびっくりしています。
そうですね。折り合いがつくことが癒しにつながるのかと、あるいは折り合いがつかないまま、それをそのままにしておくことが・・・、というようなくだりだったと思いますが、アルコール依存症の人の中で感じる癒しというものは、だいたい20年とか30年近くアルコールをやめてそういうミーティングにずっと参加し、自分の過去と向かい合い、そして周りの人たちと溶け込んでいくような、そういう感覚を持った人たちとつき合っていくなかで、「快復」ってどんな感じですかって僕が聞いた時に、「不思議なものをそのまま不思議だと思える」というふうに言っておられたのが、僕の心にとても残りました。
今日ここに来た時に、やっぱり感じることもあるんですけど、絵を見た時に、何が描いてあるのかなとか、どうしてこんなふうに描いているのかなと。どうしてこんなふうに見えるのだろう、その感覚を持っているということが何か自分の中で何かをかき立て、でも、それをそのままにしておけるということが、何か絵と向き合う時の自分の不思議な感覚になると。それがあって、これは何となくいいでしょうとか。だから、こういうふうに描いて、こういうふうになっているんだねと解説してしまうと、その魅力が損なわれる。そういう折り合いのつかなさみたいなものを、むしろ面白がって自分はここにいるのかなと思います。わかったようなことをしゃべるよりも、わからないものをわからないままにしておけるという。こういう安心感みたいなものが癒しにつながればいいなと、私は思うというより願っています。ありがとうございました。
安彦ちょうどここの正面のこの絵からこちらのパステルの絵までは、東京足立病院のアルコール専門の病棟に入院中の患者さんたちが、毎週、病院内で続けている〈造形教室〉へ出て来て描いたものです。
本当に自分は絵は下手だし、何を描いていいかわからないと言いつつも、いろいろな人が、画用紙に線を引っ張って、それを片っ端から埋めていく。午前も、午後もずっと描いているのです。それを病棟に持っていって、またやり続けている。それをみて、まず主治医が、この人がこんなに何かに集中したり、いろいろな思いがけないことをするということで驚き、次に病棟の専門の担当の職員がびっくりしていましね。
それから、この作品を版画に彫って刷った人は、もと大工さんでしたか。だから、刃物が好きなんだなと思って、版画というものがあるけど、と声をかけました。そしたら版画を彫りだした。ベニヤ板を床に置いて熱心に彫り続け、(造形の時間外にも)続けたいと言ったので、そこの病棟医が思いもかけず病棟にベニヤ板を持ってきて、「面会室でなら彫ってもいいから」といって、そういうことをやりだした。
また、この方はもう70歳近い女性の方で、絵を描くなんて夢にも思わなかったけれども、やっぱり一日中やっていると、自分の気持ちが何かそこに集中し、思いがけない自分の内在している表現が出てくる。このタイトルは『家を支える人』ですかね。それから、この人は刃物で何か彫ったり、刃物を研いだりする時に一番ほっとするというので、誰かに絵を描いてもらって、多色刷り版画にしました。
そういう意味で、僕はいつもアートというのは、教育や療法としての、というものじゃなく、いろいろな素材や出会いを用意しておけば、その人なりに何か自分にあるものを表出、発掘し、もうひとりの自分と出会うことができると思っている。そんなことで今回、この壁面をそういう意味で展示できてよかったと思います。
では、また会場の中で、いろいろ作品の前でお話を続けられるかと思います。どうもありがとうございました。 (終了)
※第3回展の会期中に計4回、行なった座談会のうちの一つを、今回、文章に起こしました。