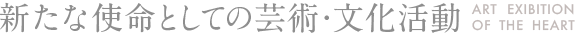第6回「心のアート展」の副タイトルは「臨“生”芸術宣言!」である。つねづね〈造形教室〉主宰者である安彦講平さんの「心のアート展」における構成力、演出力というか、出展作品を一つの方向に束(たば)ね収斂してゆく文章のセンスには感服している一人なのだが、今回の「臨”生”芸術宣言!」にも心をうばわれた。
それは、私自身が一年前にクモ膜下出血にたおれ、いわゆる臨死体験を味わったことにもいくらか起因するだろう。私には今回の「心のアート展」を、「臨“生”芸術宣言!」と位置づけた安彦さんの決意がよくわかる。「臨“生”芸術」とは、「心のアート展」にならぶ出品作者たちの、「今ここに自分は生きている」という宣言に他ならない。いつか実行委員の荒井裕樹さんもいっていたけれど、それは文字通り、自らの存命を自己確認する行為であり、「客観的に測ることも量ることも計ることもできない」「しかしそこに確実に在るというものを描き出す」営みへの自己投入なのである。
私はクモ膜下出血でたおれたとき、一瞬「死」を意識した。それは当然のことながら、自分の心身が「生」に背をむけ、「死」という未知の闇と向い合うという恐怖、畏怖の意識であり、けっして「自分が生きた70余年の人生の終焉」を意識するなどというものではなかった。迫りくる「死」を前に、私が生きた「70余年」などはほとんど無に等しいものであった。あとから考えると、そこで私は、よくいわれる「お花畑」や「三途の川」をみたような気もするのだが(私の場合は遠い夜空に打ち上がる花火のようなものだった気がする)、少なくともそれは臨”生”の記憶ではなく、臨死下における幻覚にちがいなかった。とするなら、「心のアート展」の出品者の、一種の存命記録とでもいうべき作品の数々は、やがては無に帰趨するであろう自らの生の証(あかし)を、自分の眼ではっきりと確かめ、おのおのの造形力、創造力、想像力によって表現した、今日現在このときかぎりの「命の瞬(またた)き」なのである。
さて数日前、安彦さんからご丁寧な便箋3枚ものお手紙をもらって(忙しい方なのに3枚も!)恐縮しているところだ。文面には「心のアート展」の図録への拙稿の依頼とともに、同展の<特集展示>コーナーに、私の「信濃デッサン館」で収蔵する大正期の夭折画家・関根正二(大正8年に20歳2ヶ月で死去)の作品を展示したいとの申し出が書かれてあった。これまでの「心のアート展」でも、私の好きな櫻井陽司さんの作品や、フランスの精神科病院内で長く活動を続けてきた「アトリエ・ノン・フェール」を招くなど、安彦さんの<特集展示>に対する思い入れの深さはよく知っている。ある意味「心のアート展」は併催される<特集展示>コーナーとのコラボレーションによって、初めて成立する展覧会であるといってもいいだろう。
それに、大正期の天才画家といわれる関根正二の、結核に冒されながら描いた狂気スレスレの自己凝視の絵こそ、「臨“生”芸術」とよぶにふさわしい究極の一作であろうという安彦さんの考えにも賛成である。こんな栄誉ある申し出を断れるわけはない。
しかし、一つやっかいな問題がある。現在「信濃デッサン館」に収蔵されている関根正二の作品は10点(関根の現存作品は油彩画をふくめても40余点といわれる)ほどなのだが、いづれの作品もかなり劣化や褪色がすすみ、とくに(おそらく安彦さんが最も懇望されていると想像する)関根正二の16歳のときの、自らを眼光するどく凝視しているペン・デッサンの傑作「自画像」の傷みはかなりはげしい。ために、ここ30年近くは門外不出としてきた作品なのである。はて、これを東京・池袋の会場に無事に運びこめるかどうか、果たして一週間の展示に耐えられるや否や、頭をかかえているところなのだ。
きっと私は、第6回「心のアート展」の展示作業の当日、関根正二のデッサンの風呂敷包をかかえて信州の山を下り、朝早い新幹線にのることになるだろう。