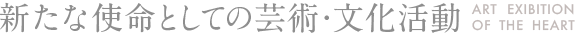「絵が生きることのすべてだった。絵しかない。そういう人生だった」。堀井正明の63年の生涯を、実姉は開口一番そう振り返った。堀井は1951年、東京都八王子市に生まれた。会社員・公務員として務める父は、かつて画家を志していたこともあり、日々の仕事の傍ら自宅ではよく絵筆を握っていた。母もまた絵を描く人だった。両親は息子にも絵を習わせたり、親子で個展を開いたりするなど、芸術を愛した家族だった。
幼少期の堀井は、「両親自慢の息子」だったという。学校の成績が良く、スポーツも万能。小学校では水泳、中学校ではテニスに打ち込み、共に八王子ではかなりの成績を残している。進学した高校では忌野清志郎や三浦友和らと同級だった。テニス部の部長として活動しながら絵も描いていた堀井は、文武両道で同級生からはうらやましがられることもあったという。
高校卒業後は美術大学への進学を選び、多摩美術大学油絵科に入学する。よき学友たちにも恵まれ、大恋愛もし、大学時代は彼の人生のなかで最も充実した時間だったようである。卒業後は美術教師として神奈川県の公立中学に奉職する。当初は授業の合間を縫って自身の創作にも意欲を見せていたが、次第に学校での多忙さに疲れ、また上司や同僚との関係の難しさをたびたび口にするようになっていった。この頃から次第に異変が目につき始め、温厚な性格だったはずが急に怒りっぽくなったり、誰かから狙われているという妄想を抱えるようになっていった。結局、25歳のときに発病して退職。以降、精神科病院への入院・通院を続けることになる。
失職と入院を経験した堀井はその後、自宅を改装したアトリエ内で絵画教室を開く。10年ほど続いたが、次第に自分の絵ばかり描くようになってしまったことで生徒が離れていった。絵画教室を閉じた後は、精神科への入退院を繰り返しながらも、公募展への出品や個展を開催するなど、絵は描き続けていた。
そんな堀井の絵に対する執念と奇行に、家族は悩まされた。画材をツケで際限なく購入し、スケッチブックに描いた絵を一枚一枚額装するなど、絵画の制作については湯水のごとくお金を使うため、年末には多額の請求書が両親宛に届いた。作品がアトリエに収まらなくなり、廊下にも隙間なく作品が立てかけられるなど、家中が作品で足の踏み場もないほど埋め尽くされた。その一方で絵以外にはまったく無頓着となり、身なり気にしない服装でタバコを買いに行くこともあった。ピカソに心酔して「自分は天才だ」「自分の絵はそのうち高く売れる」「文化勲章をとる」と豪語していた。「パリに行く」という話を取り合わなかった母親に激怒し、追いかけ回したこともあった。この頃の堀井は、姉の子どもをモティーフにした油絵やペン画などの作品をいくつか制作している。堀井はこの甥と姪をとてもかわいがり、子どもたちも懐いていた。
平成9年頃、堀井は北野台病院に入院する(はじめての入院以来かかっていた病院が、精神科病棟を高齢者病棟に転換したため)。その後、画材を買うために一時的な外出をすることはあったが、退院することはなく一度も自宅に帰ることはなかった。入院中も作業療法室や病室内で制作を続けていた。ただ、大きな油絵を描く気力は戻らなかったようで、姉からの差し入れのスケッチブックや自由帳に、木炭や鉛筆、水彩やアクリルなどで、その時どきの心象風景を描き留めていた。そのうち堀井は、安価なお絵かき帳やメモ帳のようなノート類を好んでリクエストするようになったという。姉がノートを差し入れると、表情がほころんだ。甘いものと画材があれば、安心した様子だった。「○」や「三日月のような模様」を少し描いては、その一枚一枚にサインをしたという。
堀井は人生の多くの時間を絵と共に過ごしてきた。もともと、寡黙で温厚な人柄のため、病院内でも黙々と絵を描いていたという。晩年は身体的な衰弱も進み、何度も肺炎を繰り返した。そのせいか、実年齢よりも10歳以上は老けて見えた。2014年7月18日、永眠。堀井の絵を慕った病友が、一晩中、涙を流していた。姉は、「かわいそうな一生だった。かつての友人や関係者たちが、だんだん正明のことを話題にしなくなり、次第に存在自体を忘れていく。そういうことがとても悲しかった」と語る。しかし一方で「最後まで絵を描くことが出来て、満足だったのかも知れない。大好きな絵をずっと描いていられたんだから。絵が生きることの全てだった。正明にとっては幸せな人生だったのかも知れない」とも語った。
(心のアート展実行委員会)