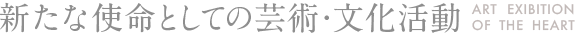「もっともっと感動する。何でもまっしぐらに描けるように目茶目茶にまっしぐらに勉強したい。」
「万巻の書を読むことは、絵の具を使うことよりも大事。」
「僕は人に教えて銭を受けようとは思わない、おしえて教えられるものでないものを教えるとはおかしい。」
「90以上生きて、線一本引いて死のう。」
そう言って、最期まで生命の炎を燃やし続けた画家。その活き活きとした清浄なる炎は、絵画の様式や技法の差異を超え、或いは時代を超えて、観る者に感動を与え続けるでしょう。
平成12年(2000)に画家が亡くなって約2年後、その作品にはじめて出会った私は、其処に満ち、溢れんばかりの力と生命の躍動、デッサンの線一本に宿る清らかなる光といった言葉に尽くせないものを感じました。その静かに、しかし確実に、私の内に雪のように積もる感動は、何者かにつき動かされるようにして、ギャルリさわらびの開廊へと繋がっていったのです。
『ガードのある風景(神田駅附近)』の実物を前にしていると、詩を歌い詩情に流されず、また、現実をえぐるような視線を持ちながらもその頑強さに固執せず、両者ギリギリのバランスの上に立ちながら、悠々と遊ぶ境地に、感服させられます。一本の線の厳しさと清らかさに自然と背筋を伸ばされる思いです。ひとつ間違えれば、全てを失うような崖っ縁に立ちながら、その素振りを見せずに、雄々しく、そして潔い。
かつて、ゴッホの絵について画家は、「画が彼の一生の生活の記録」であり、「画はそういうものでなければならぬ。」と言いました。清貧の生活を守り、家族を支え、社会の問題にも積極的に関心を寄せ、絵のモチーフの殆どは身の周りのものや人であり日常の風景です。昭和30年(40歳)頃から30年に及ぶ闘病生活は、平井富雄精神医学博士との出会いによって回復を克ち得、その間も弛むことなく描き続けました。「自分が少年の頃からすきな画家 ゴオホ(ゴッホ) ムンク (佐伯)祐三 三人共 自分と同じ病気とは苦しいことである」と、当時の胸の内を吐露しつつも、精神医学書を読むなどして自らの病を冷徹に分析してもいます。誰からも「おしえられるものでないもの」。「万巻の書を読」み、「目茶苦茶にまっしぐらに勉強」し、「もっともっと感動する」。櫻井陽司。その生き方が作品であり、作品が生き方です。
自らを「はじめから終りまで画家だと思っていない」とも語っている櫻井は、既成画壇と距離を置き、その名が世に出る機会も有りながら、それを敢えて避けるようなところすらあり、真の芸術の自由とは何か、生きるとは何か、ということを、深く考えさせられます。
「自分の絵は、日本人の油絵になると思う」という言葉を櫻井は残しています。彫刻家のアルベルト・ジャコメッティの言葉に共感していた櫻井ですが、其処に見る「(セザンヌは)主観を捨てて自然を忠実に模写しようとしたのだ。しかし結果においてセザンヌの絵ほど忠実に模写しようとしたのだ。しかし結果においてセザンヌの絵ほど個性的なものはほかにない」という、いわば無私の精神、或いは、個性的であろうとするのではなく、自然と一体となるこころのありようは、日本の歴史や伝統文化の中に、様々なかたちで顕れたものでしょう。美術に限らず、多くの外来の文物を受容し、換骨奪胎させ、他に無いものをつくり出すのが、日本の大きな特質ですが、油絵の具という外来の材料によって、何処にもない、日本人の油絵を描くという点で、櫻井は大きな成果を残し、また、それによって、日本人のみならず、多くの人々に力を与えてくれるでしょう。
「頭の中にコンパスや定規のある様な、用意された絵はあんまり好みません。対象にぶつかって飛び散った血液のような、切実な絵が好きです。」
頭の中でこしらえ、小手先でこしらえるような作品には、「血」が通っていないでしょう。やむにやまれぬ「血」こそが、芸術という「歌」を奏でるころが出来るのではないでしょうか。
この度の「心のアート展」では、安彦講平さんのご推挽を得て出展させていただきました。安彦さんはじめ関係者の皆様には、この場をお借りして御礼申し上げます。