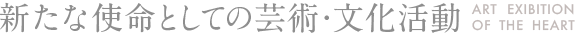……この絵はですね。3回目の入院の時の体験がもとになっているんです。強制入院で保護室に入れられ、強い薬で抑えられ、手足を縛られて身動き出来ない状態だったんです。10日か2週間位経った頃、ドアがすーっと開いて、スケッチブックを差し出してくれた人がいたんです。そのときは誰だったか分からなかったんですよ。強い薬で記憶が消されているので、はっきり覚えてないんですよ。後から聞いたらそれは安彦先生だった、と分かったんですが……
これは、ドキュメンタリー映画『心の杖として鏡として』の前半の場面で、名倉さんが「“癒し”としての自己表現展」のギャラリー・トークの会場で自作の『幸への黒い扉』と題された100号の大きな油絵を前にして語っている言葉である。
退院後、竹ノ塚(東京・足立区)のアパートから2時間以上もかけて、毎週八王子・高尾にある平川病院のアトリエに通い、絵を描き続けた。専用のイーゼルに立てかけた大きなキャンバスにへばりつくようにして、まるで自分の身体から絞り出したまんまのような赤・黒・黄色の絵の具を分厚く盛り上げて縦・横の線を刻み込むように描いていた。その姿がいまも鮮明に思い返される。名倉さんの言葉が続く
……描きかけのこの絵を観た人に、「これ何?」と言われ、自分でもこれだけじゃって思って、ここに黒で描いたのが窓というか、病院の出入口の扉ですね……
鍵と鉄格子に閉ざされた保護室から一時一刻(いっときいっこく)でも早く出たい。が、退院してここからの出口であり、そして再起、再出発のための入り口であるはずの向こう側は黒く、暗くて先が見えない。その時の苛酷な体験を大きな作品に刻み込んでいる。
真っ黒な、汚水の悪臭に満ちた下水道のトンネルの中を彷徨(さまよ)い続けている若い男女の一団が前方にほの明るい光を見つける。歓声をあげて駆け寄る。出口と思ったトンネルの先の丸穴は、鉄格子で塞がれていて出るに出られないどんづまりだった。トンネルの真下は川。その川の向こう側の景色は遠く隔たった彼方の別の世界の様に映じている。これはナチス占領下におかれたワルシャワでのレジスタンス地下運動の悲劇を描いたアンジェイ・ワイダ監督のポーランド映画『地下水道』のラスト・シーンだ。今から半世紀前、私の学生時代、激動の1960年代に観たワイダのもうひとつの傑作『灰とダイアモンド』とともに一生忘れられない名画だ。
『幸への黒い扉』と『地下水道』は時代も国籍も遭遇した状況もそして表現様式も異なるが、二つの作品は奇しくも、共通の主題を描き、歴史的、そして個人の重大な体験をありのまま証言している。出口無しの、暗く、重たい現実と向き合い、描かざるを得ないというポジティブな意志が刻み込められている。内容や結末が暗いからといって、ただ「暗い」のではなく、だからこそ重く深いのだ。その先が閉ざされているから「希望が見えない」のではなく、自分の置かれた情況を見つめ、ありありと表現されている原点からの声が観る者に、訴え、問題を突きつけてくる。